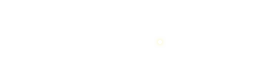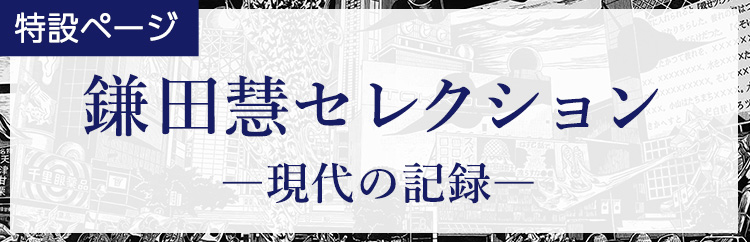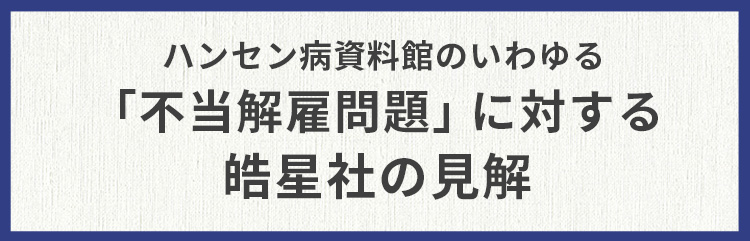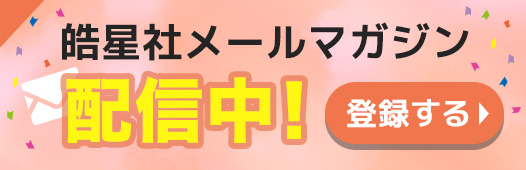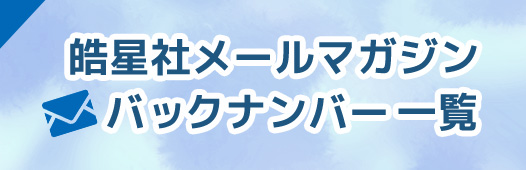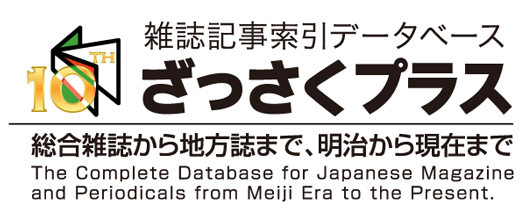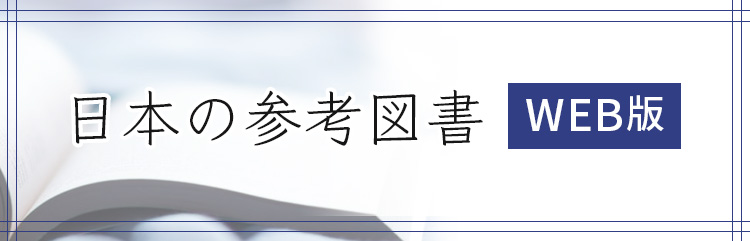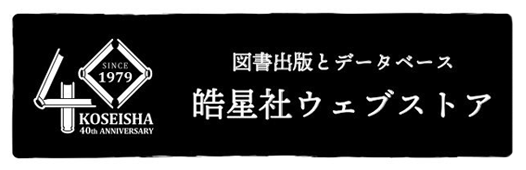Webコラム「 メルマガバックナンバー 」一覧
- 第1回 白雲、13歳の詩
- 公開
今年2022年は、詩人・長澤延子の生誕90周年という節目の年です。長澤延子は群馬の桐生市に生まれ、戦後まもなく17歳という若さで夭折。しかし、彼女の清冽な詩は、死後友人らによって刊行された遺稿詩集『海』によって広まり、6 […]…続きを読む
- 第10回 出版界を震撼させた全日空羽田沖墜落事故
- 公開
河原努(皓星社) ■出版界で一番の大事故 出版関係者の訃報調査をしていると、全く同じ日に亡くなっている人を見つけることがある。光文社社長を務めた五十嵐勝弥と地人書館創業者である上條勇は同じ昭和50年1月2日に亡くなってい […]…続きを読む
- 第9回 労組が作った饅頭本――三省堂の横山茂と笹沢健
- 公開
河原努(皓星社) ■饅頭本の多い分野は? 原稿を集めて、編集をして、印刷をして1冊の本を作る。それには今日でも最低で百万円程度は必要である。その事実をふまえると「饅頭本」――追悼録を古書業界でこういう――は売り物ではない […]…続きを読む
- 第9回 次世代デジタルライブラリーの感想――日本語版Googleブックスの試み
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■はじめに 前回予告では「索引の排列」について取り上げるつもりだったが、なんとびっくりGoogleブックスもどきβ版を日本の国立国会図書館(NDL)が公開したので、ここに紹介したい。こうい […]…続きを読む
- 第3回 71年前の友人(文藝誌「園」主宰 河村実月さん)
- 公開
向島から淡いピンク色に滲んだ空が尾道大橋へ、そしてこちら側の山まで広がっている。空は次第に色を濃くし、朝日が山の隙間から覗いて昇っていくまでは一瞬で、暗い部屋にあったはずの炬燵の上のみかんも今では朝日のよう […]…続きを読む
- 古本趣味と赤ん坊と。 カラサキ・アユミさん
- 公開
古本と古本屋への愛を4コマ漫画で綴った『古本乙女の日々是口実』(2018年、小社刊)の著者であるカラサキ・アユミさんに〈新年の抱負〉をテーマにご寄稿いただきました。昨年にはお子様も生まれ、新たなステージへと一歩踏み出すこ […]…続きを読む
- 友よ、私が死んだからとて 福島泰樹さん(歌人)
- 公開
群馬の桐生市に生まれ、戦後まもなく17歳の命を断った詩人・長澤延子。彼女の清冽な詩は、死後友人らによって刊行された遺稿詩集『海』によって広まり、六〇年代という叛乱の時代を生きる若者たちの胸に深く刺さりました […]…続きを読む
- 第8回 私の恩人――日外アソシエーツ創業者・大高利夫
- 公開
河原努(皓星社) ■いまから20年前…… 地方の公立大学でぐーたら本を読んでいた私は、4年生になって「就職」という当たり前の一大事に直面して、とりあえず自己分析をしてみた。人にない自分だけの取り柄を考えると、それは「高校 […]…続きを読む
- 第6回 本好きはうつへと至る一里塚
- 公開
■『双極II型障害という病 -改訂版うつ病新時代-』内海健著、勉誠出版、二〇一三年 読了 2014/4/30 目次 http://bensei.jp/index.php?main_page=product_ […]…続きを読む
- 第8回 回答の手間ヒマを事前に予測する――日本語ドキュバースの三区分
- 公開
小林昌樹(図書館情報学研究者) ■主題と時間と空間と ベテランのレファレンス司書は質問を聞いた瞬間に――無意識的にせよ――答えがでるまでのコストや困難さを予測している。これは、経験的に察知できるようになるものだ。もちろん […]…続きを読む