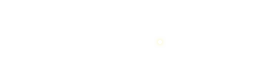神保町のんしゃら日記17(2025年5月)
1日(木) 『鎌田慧セレクション5 自動車工場の闇』の見本の日。収録した『自動車絶望工場』は鎌田さんの出世作だ。ちょうど、日産のニュースが続いている時期でもあり、期せずしてタイムリーな発刊となった。鎌田さんはあとがきでこう書いている。
「わたしの関心は、繁栄を支えたベルトコンベアの労働過程のなかでの、人間の状況である。労働者がどのように扱われてきたのか。労働の標準化、人間の機械化、生産性のためだけに、人間を支配する。資本主義の極限を求めたなかで、人間と社会にどのような変化があったか、ということだった。」
省力化、そして無人化の現時点での極地はAIだろう。この人間による労働の否定を、人間性の否定にむかわせないで行くことができるのか。セレクションでありながら、鎌田さんの問いはいつも現在のものだ。
4日(日)ハンセン病資料館友の会の活動の日。沢知恵さんにご講演いただく。
7日(水)実家から荷物が届く。山菜類や福田パンなど岩手の恵み詰め合わせ(感謝)。行者大蒜は豚肉と炒め物に、しどけはおひたしに、コシアブラはほろほろにする。ほろほろは、コシアブラと胡桃と大根の味噌漬けをひたすら細かく刻んで和えたもので、山菜料理では私が一番好きなもの。白いご飯にかけてかっこむ。(ほろほろに使う山菜は何でもいい。しどけの葉でもいいし、地域によってはウコギを使うこともあるようです)
10日(土)東京経済大学で『パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたち』刊行記念イベント。著者の早尾貴紀さんと、本書の第三部で鼎談に協力してくれてた李杏里さん、牧野久美子さんの3人のが登壇し、「植民地主義」をテーマに対談では話しきれなかったことも話していただいた。150人規模の教室がほぼ一杯になり、時間内に解答しきれないほどの質問が寄せられた。本も多くの方が買ってくれるか、持ってきて参照しながら聞いていた。ありがたく誇らしい。しかしそれと同時に、今まさに行われていることに対する無力さを思うとき、その落差はあまりに大きい。これが商売として成り立つ世界では、本当はいけない。
11日(日)浜野佐知監督『金子文子 なにが私をこうさせたか』のクラファン試写。『なにが私をかうさせたか』を読んだ時は、朴烈への愛の言葉に違和感があったので、その違和感が解決されて自分の中で金子文子像が立ち上がってきた。菜葉菜さんの演技が素晴らしかった。
13日(火)ジャバラの花が咲いた〜!昨日まで小さな蕾だったはずのそれが一気に開花して、甘い柑橘系の香りを放つ。小さな蕾のわりに花は大きい。朝からぱっとあかるい気持に。
14日(水)始発で家を出て飛行機に乗り、福岡出張。丸善雄松堂さんと大学図書館、県立図書館などを回る。夜、焼き鳥でビールを飲んで倒れ込むように熟睡。
15日(木)今日は熊本。昼ごはんは出張の楽しみのうちの一つでもある。営業の方と「武蔵茶屋」で高菜定食。ひもかわのような平たいうどんと高菜ご飯のセット。武蔵うどん、と看板にある通り、九州のうどんだが出汁系ではなくつゆも関東風だ。うどんにはお餅も入っていて、すっかり満腹に。むかしながらのお土産物やさんが併設されており、一万円もする木刀!が売っている。こういうのがいい。
終了後、市電に乗って橙書店さんへ行く。いつも仕入れてもらっているけれど訪店ははじめて。店主の田尻さんと常連さんらしいお客さんが本の話をしているのを心地よく聞きながら2、3冊と、橙書店さんのオリジナル一筆箋を選んで買う。晩御飯は福岡に帰って…と思ったのだが、橙書店さんのすぐそばに良さそうな居酒屋を見つけ、夕飯を済ませてから福岡に帰る。大豆の煮たの(ざぜん豆というそうだ)が美味しく、とってもお酒にあう。90代のお母さんが現役でカウンターに立っていた。
16日(金)長崎出張。移動の車で、営業の方と家庭菜園や、コンポストや、夫婦別姓やらの話で盛り上がる(もちろん商売の話も…)。同好の士を見つけたり。数日同行していただいた皆さんと乾杯して、営業のしめくくり。あげまき貝、という貝をはじめて食べた。浅利を平たくしてながく伸ばしたような形。浅利、ホンビノス、ハマグリの中間点のような味わいでうまみが強い。今回も丸善さんにお世話になりました。
17日(土)せっかく九州にきたので、延泊して北九州の著者に会いに行く。火野葦平記念室や火野葦平の旧宅にも足を伸ばす。
18日(日)最後の飛行機(一番安い)で帰宅。兎にも角にもシャワーを浴びて寝る。水曜日から今度は東北。明日は朝一で洗濯機を回さなければ。
21日(水)今日から、今度は東北の営業。今日は仙台。明日は仙台と山形を半日ずつ営業して、岩手の実家に帰省する予定。
23日(金)岩手県内で「書庫拝見」の取材に同行。個人的にも思い出のある場所だったのでことのほか感慨深い取材となった。
24日(土)盛岡のブックイベント、モリブロ1日目。モリブロは一度終了していたが、タウン誌の「てくり」20周年を記念に今年ふたたび開催されるそうで、出展してみることに。会場の岩手公会堂は県庁の隣にある。1927年に、日比谷公会堂などの設計をした建築家の佐藤功一の設計で建てられた。古くていい建物で、ここで、こんなイベントをさせてもらえるとは嬉しい。盛岡在住の著者の方々も、ブースにきてくださる。向かい側では遠野の出版社の富川屋さんが出展している。代表の富川さんは地域おこしの仕事がきっかけで遠野に移住し、遠野物語にハマり、今度亜紀書房から、遠野の獅子踊りの本を出されるそうだ(6月発売『シシになる。──遠野異界探訪記』)。地元とはいえ、まだまだ岩手でしらないこと・人がたくさんある。
25日(日)モリブロ2日目。母が販売の助っ人にきてくれる。以前お世話になった方が立ち寄ってくれたり、高校の同窓生と再会したり、地元出店ははじめてだけど、他とは違った嬉しさがある。南陀楼さんのトークでも本がたくさん売れた。2日間の累計もまずまずでした。地元貢献、などができるゆとりも能力もないけど、また何か一緒にできる機会がありますように。
26日(月)午前、書店さんで商談。昼の新幹線に乗って会社へ。昼ごはんに福田パンを2つ食べる。ハム&ポテトサラダと、パインバター。さっぱりしたパインを練り込んだバターと、塩味のパンがとってもあう。帰社て取引先に書類を届けるために外出すると、「ぐるくん」と書かれたTシャツを着た男の人があるいてきた。ぐるくん……沖縄出身の人だろうか、みょうに頭にのこって、ぐるくんがあたまの中をぐるぐるまわる。
今月は2回出張があったが、私がいなければいないで、現場はなんとか回るものだし、そうでなくてはいけない。今年度はそれを目標にして出張にでたので無事達成しつつある、と言えそうだ。
27日(火)モリブロで買った本をめくる。はやしみかんさんの『なんだりかんだり のんだりくったり』(まちの編集室)がいい。すごくいいい。食べ物や飲み物をめぐっての、盛岡やお江戸(とみかんさんはいう)のエッセイ。「てくり」に連載されていたものだそうだ。私の大好物の「ほろほろ」の話もでてくる。それにしても、いいタイトルだなあ。この「だり」ってなんだと、岩手以外の人にはよく言われるけど、「だり」は「だり」でしかない。あえていえば「でも(なんでもかんでも、のでも)」が近いんだろうけど、やっぱりちょっと違う……。みかんさん、最近亡くなられて、遺稿をまとめた形のようだ。もっとまとまった形でも読みたかっただけに、残念だ。
28日(水)モリブロで買った、かちどきどんぐりちゃん作品集『とっこ』(信陽堂)を読む。被災地を舞台にした絵物語。「とっこ」は糸がからまるという意味の方言だそうだ。物語、というものの効能の一つは、それを読んだ人の心の傷が癒えることだと思う。いや、傷を治したいと思って読み始めるわけではないし、傷自体を認識していないことも多いから、期せずして「癒えてしまう」と言った方がいいかもしれない。『とっこ』はそんな物語の効能が十分に発揮された本だと思った。こんなに素敵な書き手の人が岩手にいたんだなあ。丹治さん、いい本作られるなあ。
30日(金)夜、友人一家がやって来て一緒に夕飯。追浜住まいということから、日産の工場閉鎖のニュースはよく見ているという。大きな工場が閉鎖されるとなると、そこに雇用されている人たちはもちろん、税収が変わって市民の暮らしにも大きな影響がでる。鎌田さんのルポを読んで思うのは、これらは昔の社会問題の話ではなく、今の一般市民である私や、友人たちの、現在進行形の問題だということだ。
31日(土)雨の土曜。少しの晴れ間をぬってそら豆をすべて収穫した。途中、病気にやられてしまったものの、莢をはずした状態で4キロの収量があった。早速、茹でたてを食べる。しっかりとした豆の味と香りがした。