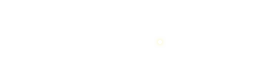第35回 当代随一のフリ手、“松要さん”こと松浦貞一
河原努(皓星社・近代出版研究所)
■『松要さんの思ひ出』
前回は中興館創業者・矢島一三の喜寿と金婚を記念して作られた非売品の随筆集『八洲漫筆』を取り上げた。この手の“饅頭本”で、近代出版史を研究する上で特に重要なものに何があるだろうか? 『八洲漫筆』は矢島が戦時中の出版社統廃合の責任者であり、その証言があるため重要なのだが、他に思い浮かんだ重要な一冊に『松要さんの思ひ出』(全国出版物卸商業協同組合、昭和30年)がある。「松要さん」は“まつよ”さんと読み、同書は大阪で特価本の問屋を営んでいた松浦貞一(1886-1953)の追悼文集である。
【図1】『松要さんの思ひ出』

■特価本とは
一般に新刊書籍は再販制度(再販売価格維持制度)を取っており、新刊書店で本を買うときは全国どこでも同じ価格で買え、書店の判断で勝手な値引きはできない(その代わり売れ残っても出版社に返品できる)。では、たまにスーパーの一隅などでみかける本のバーゲンセールは何なのか? あれは古本では無く、出版社が値引き販売を認めた新刊のバーゲンセールなのだ。そこにバーゲン用の本、いわば「バーゲンブック」を供給する問屋の最大手・第二出版販売のホームページにはこうある。
バーゲンブックとは?
出版物は<定価販売>だけだと思っていませんか?
バーゲンブックとは定価より値引きされた書籍や雑誌のことを言います。書籍は一般的に再販売価格維持制度に基づいて流通されています。
再販売価格維持制度とは出版社(製造者)が書店(小売店)に対して定価で書籍や雑誌を販売するように働きかけることが出来る制度です。
つまり本は普通定価で販売されており、値引きはされません。しかし、出版社の意思により値引きの対象とされた書籍に限り、定価よりも安い価格で販売できます。そうして値引きされた本を「バーゲンブック」「自由価格本」「読者謝恩本」「非再販本」などと呼びます。
このような本は定価で流通し書店で一度並べられたが、最終的に出版社に返品され在庫として眠っていた本がほとんどです。それら休眠在庫がバーゲンブックという形で再び読者の目に触れられることが出来るのです。
こういった本は業界用語で「ゾッキ本」「かずもの」、または「特価本」とも呼ばれ、戦前から存在した。戦前は特価本の存在が今では考えられないくらい大きなプレゼンスを持っていたのに、それが現在では全くといってよいほど見えなくなっていると、近代出版研究所の小林昌樹所長からよく耳にする。いままでの研究に使われてこなかった『松要さんの思ひ出』は、実は戦前の特価本業界を研究する上での必須文献なのだ。
■「総ルビ」のありがたさ――饅頭本には珍しい
ちなみになぜ「松要=まつよ」と読むかわかるかというと、本文中に出てくる漢字には全て読み仮名が振られているからだ(=総ルビ)。 “饅頭本”はルビどころか、そもそも書かれている人物の読み方の記載がどこにも無い物が多い。なぜならこの手の本は多くの人に読まれることを想定しておらず、旧知の人に配るための本だからだ。例えば書かれた人が「岡本正一」さんの場合、その読み方が「しょういち」なのか「せいいち」なのか「まさかず」なのかを、旧知の人なら既に知っているからである。
結構な数の出版人の“饅頭本”を見てきた中でも総ルビというのは大変珍しく、この本くらいしか知らない。おかげで東京の特価本本屋の雄、河野成光館の読み方が「かわの」ではなく「こうの」だとわかった。その点でも得がたい一冊だ。
【図2】総ルビの本文
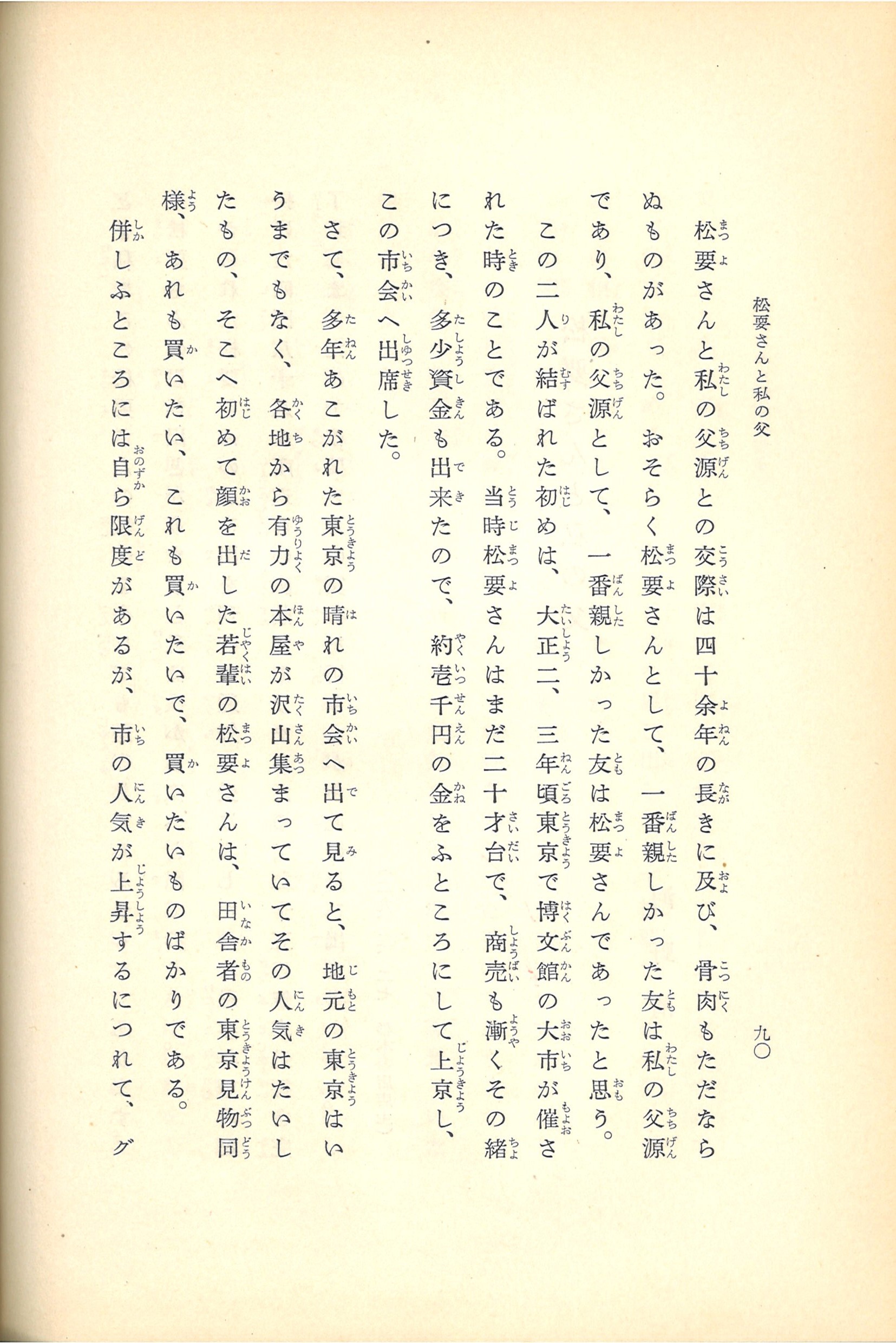
■大正2、3年頃の「大市」をきっかけに関西特価本業界の顔役へ
「松要さん」こと松浦貞一は兵庫県北条町の柏原家に生まれた。12歳の頃に大阪へ出て松浦要助の営む反古問屋の店員となる。「松要」の通り名はこの先代・「松」浦「要」助に由来する。反古とは使用済みの和紙で、これを漉き返して新しい和紙を作る。つまりは製紙原料商である。先代が急死すると、和紙の需要が減ってきたこともあって書籍商に転身。大正2、3年頃に東京で行われた博文館の大市で河野成光館主人・河野源と知り合う。
この「大市」とは何か? それについて小川菊松『出版興亡五十年』(誠文堂新光社、昭和28年)にはこうある。
図書大市の話
昔は本を扱う者を一様に本屋といい、出版、取次、小売の区別はなかつたが、出版業が発達するに従つて出版、小売の区別を生じ、次で取次業が生れて三者の分業となつた。そして出版業者は自分の出版物を売り弘めて金を早く手に入れようとし、小売業者は多く売れる品を早く安く手に入れようとし、取次業者はその間に立ち品物の需給を円滑にして口銭を稼ぐのである。これらの要求をうまく調和させて行こうというので図書市が生れた。普通に図書市というものゝうちには、新本市、古本市、見切本(残本)市、和本市、原書市、紙型市等色々がある〔後略〕。
この市で思い出されるのは、フリ式市会のときの「フリ手」のことである。フリ手は売主と買主との中に立ち、会場正面の一段高い所へ陣取つて「サアいくら」と買主に値をつけさせる。それを段々とせり上げて適当の値段「これでよかろう」という所で競落させるのであるが、これが中々むずかしく、安い値段で競落せられては、売主が堪らないから異議を唱える。もし紛糾でもすると買主は最後に買わない、撤回しろなどゝ怒り出して場内が騒然となつてしまうし、フリ手と売主が結託して、フリ手が上手に要領よく高値にでも落そうものなら、これまた買主が怒り出す。更にフリ直しをして値下げをすればよいのであるが、これが妥協の出来ない時は場内俄然大紛糾を来たす〔後略〕。(p276-278)
松浦と河野源が知り合った博文館の大市とは、実は「見切本(残本)市」で、博文館が在庫過多で「見切った」本を放出した市会だった。1000円を懐に上京した20代の松浦青年は憧れの市会でドンドンと買い進めたが、気がつくと用意してきた金の2倍近くを買ってしまっていた。今更取り消しもできず、さりとて新米故に知己も居らず、金を借りられる人もいない。先ほどまで勢いよく買っていた大阪の若者が急に塞ぎ込んでしまったのに気がついた河野が「どうしたんだい」と声を掛けると、松浦は事情を包み隠さず話した。河野は「それっぱかしの金でクヨクヨすることはない。その金は私が立替えておくから、元気を出しておやんなさい」とその場で不足金を出してくれた。以来、二人は肝胆相照らす仲となり、河野は関東を、松浦は関西を地盤に特価本業界を牽引するに至ったのだった。
このようなエピソードは『松要さんの思ひ出』ではじめてわかることである。
■市会のフリ手として
先に引用した小川の「図書大市の話」に「昔は本を扱う者を一様に本屋といい、出版、取次、小売の区別はなかった」とあるが、松浦も巧人社、近代文芸社の商号で出版業も手がけた。「国会図書館サーチ」を引くと巧人社で97冊、近代文芸社でも60冊ほど出てくる。発行人の名義が「松浦一郎」になっているものがあるが、これは貞一の長男の名前である(後に一郎は台湾から帰ってくる途中に飛行機事故で戦死した)。
しかし出版は余技といったところで、松浦の本領は市会のフリ手としてであった。これは『松要さんの思ひ出』を通して、ほぼ全員が回想している。
原田秀一(金文社専務取締役)「あの「セリ方」は神品ともいふべく出品者の身方であり乍ら又、常に買い手の身方であり、時としては出品の出版者を押えて落ち値を決定拍子木を打つあたりは長者ならでは出来ないうまさ、松要さんの徳なくしてよく成し得ぬ所であつたと追憶してなつかしくてなりませぬ」(p10)
小島重太郎(文開堂社長)「本屋の糶市といえば振り台に松要が戎様の様な赤ら顔でユーモアーたつぷりの「エーそれでは発句何程」立板に水と云う程ベラベラと口上手でもないが人心把握電気に吸付けられる様に品物が生きて、はね返って居るかの如くに到々欲しく成り、群集心理は人が買出すとうづうづして来て吾一と飛付て来ました。振手が替ると頓と人気が落ちて場内しんとして活気が消えて来る程昔は一声千両現在は何百万の価値で出版界随一の人気男、本屋の至宝松要の後に続く者は当分養成出来ないでせう」(p72)
河野清一(河野書店社長)「日本中のあらゆる市会にひき出されて、「振(ふり)」の大役をつとめた。松要さんが出ると出ないとによって、市会の売上げに大きなちがいを生ずるとまでいわれた」(p93)
【図3】『松要さんの思ひ出』口絵にある市会の風景

■家庭の事情――饅頭本には書かれないこと
こうした褒め文句の一方で、いろいろ歯切れの悪い表現にもぶつかる。関係者を集めた座談会でも、次のような微妙な口ぶりがぽつぽつとある。
斎藤佐次郎(金の星)「あんな熱情家は私ども大勢の友人の中で見たことがありません。熱情家というよりは、純情家ですよ。実に純情そのもので、またその純情のために、ずいぶん自分の生活を不幸にした人だとも思うのです」(p104)
倉間勝義(日本特価書籍)「そこであの人の半生記を聞いたです。それまではあの人がどういう経歴の人であるか知らなかつたが、あの人はそこで涙を流して話された。やはり体も悪かつたから感傷的であつたのでしようね。それでいろいろなことを聞いているうちに、あの人の性格から私が感じたことは、親分肌で、人情もろくて、世話好きで、義理人情を非常に重んずる人で、それが業界で皆に立てられた原因の一つだとまず感じたし、同時にそういう性格が大勢の女の人をつくつたし、いろいろな問題を起す元になつたのだろうということをそのときに考えたです」(p141-142)
坂東恭吾(良文堂)「松要さんのお店から出ている人は松要さんそのものには絶対に心服をする。しかしどういうものだか奥様運には非常に不運な人でした。しかしこれも一つはやはり運命づけられていることだからしようがないでしようけれども、松要さんの女房運の悪いのは、先ほどから皆さんの言われている松要さんのあの情熱の気分が大いに禍いしている」(p144)
掉尾を飾った沢田一雄(沢田正進堂社長)の文章「松要さんの悩み」には次のようにあった。「いつも上京の車中及び宿等でよく御自分の過去の成功談、失敗談を話して頂き、それが私の何よりの楽しみでした。その失敗談の一つに御自分の悩みの第一は家庭にある点、年と共に痛切に感じられ、御自分がよい手本だから女に対する戒を注意されました。この悩みの一部を打明けられたお手紙を原文のまゝ記載さして頂きます、松要さんは奥さん運が悪く次々と死亡されて第四夫人が最後でした」(p157)。正直、4回結婚できるのは大したものだと思うが……。
そして盟友・河野源の長男である河野清一の文章には「この間、大正七年に松要さんの一身上に大きな過ちが起った。これは松要さんの生涯における最大の不幸であったが、この時には私の父もかけつけて、色々と心配をした」(p93)とあった。
その後、金沢文圃閣から復刻された出版業界紙の嚆矢『出版タイムス』の最初の巻を読み始めた私の目に、「松要さん」の名前が出たある記事が飛び込んできた。“一身上の大きな過ち”とはこれか、と思ったが、どういう過ちかはここでは述べないこととする。それにつけても「松要さん」はある種の激情家であり、憑依タイプのフリ手だったと思われる。
なお、『松要さんの思ひ出』は金沢文圃閣から小林昌樹さんの解説を付して復刻されるとのことである。
○松浦貞一(まつうら・ていいち)
旧姓=柏原
松要書店主人 近代文芸社創業者
明治19年(1886年)10月21日~昭和28年(1953年)11月11日
【出生地】兵庫県加西郡北条町(加西市)
【経歴】12歳の頃に大阪へ出て松浦要助の営む反古問屋(製紙原料商)の店員となり、20歳頃にその養子となる。「松要(まつよ)」の通り名は先代・「松」浦「要」助に由来する。先代の没後、和紙の需要が減ったこともあって書籍商に転身。書物の特価本(赤本)問屋として東京の河野成光館と“東の河野、西の松要”と並び称される最大手に成長、特価本業界では新刊を扱う四大取次に匹敵する存在になった。セリ市においては、書籍を次々と捌いていく業界随一の名フリ手として名を馳せ「松要さんが出ると出ないとによって、市会の売上げに大きなちがいを生ずる」とまでいわれた。赤本の流通の傍ら、昭和4年近代文芸社の商号で出版業にも乗り出し、吉井勇、斎藤弔花らの文芸書から、辞書・料理書・手芸書などまで幅広く手がける。16年取次業が統合され日本出版配給(日配)が設立されると、赤本を取り扱う大阪支店博労町営業所長を務めた(敗戦半年前に退社)。没後、追悼集『松要さんの思ひ出』が編まれた。
【参考】『松要さんの思ひ出』全国出版物卸商業協同組合/1955.11
○松浦一郎(まつうら・いちろう)
巧人社 日月書院
明治43年(1910年)2月9日~没年不詳
【出生地】大阪府大阪市
【学歴】小野町中学卒
【経歴】関西特価本業界の顔役である松要書店主人・松浦貞一の長男。巧人社、日月書院の商号で出版業も手がけた。戦争中、台湾からの帰国途上に沖縄上空で飛行機事故のために亡くなった。
【参考】『松要さんの思ひ出』全国出版物卸商業協同組合/1955.11
☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。