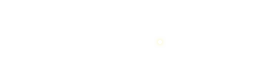第5回 人類学が「書かれたもの」を見る時、書物論もまた人類学を見返しているのだ
■ティム・インゴルド『ラインズ 線の文化史』工藤晋訳、左右社、二〇一四年六月
読了 2014/9/17
目次: http://sayusha.com/catalog/books/longseller/p9784865281019c0039
「記述 Writing」(=書記、と訳して貰ひたかったところ)や「刻印 inscription」を論じた本書は、文字論・印刷論・中世読書論を含み、オング(『声の文化と文字の文化』)やセルトー(『日常的実践のポイエティーク』)やカラザース(『記憶術と書物』)やルロワ=グーラン(『身ぶりと言葉』)やハヴェロック(ハヴロックと表記、『プラトン序説』)が参照されるので、書物史好きには馴染みやすくすぐ読める。そもそも著者は人類学者で、人類学や民俗学が対象としてきたのが無文字社会や口承である以上、書字の有無こそはその臨界点として意識されるところ、おのづから書物論とは好対照をなす。あんまり対比図式を誇示するとジャック・グディ『未開と文明』(吉田禎吾訳、〈岩波現代選書〉一九八六年十月、原題 The domestication of the savage mind )のやうに「大分水嶺理論」との批判を受けるにしろ、だ。本訳書は世評高く書評も随分出たやうなのに、エクリチュール論やリテラシー論につながる線を強調する批評が目立たないのは、書物史的な教養(リテラシー)がまだまだ留意されてないといふことか。遺憾なり。
点と点との連結として考へられがちな「ライン」をベルクソン流の生成論によって賦活し、身ぶりの軌跡や道に沿った動きとして捉へ直す。そこから、徒歩旅行 wayfaringと輸送 transport、網細工(メッシュワーク)とネットワーク(網目)、系統 pedigreeと系譜 genealogy、カリグラフィーとタイポグラフィ、といった二項対立で概念が提出されてゆく。「こうした近代批判はいかにも典型的」(千葉雅也評、日本経済新聞2014年7月13日)ではあり、手書きを尊ぶ石川九楊信者辺りに歓ばれさうだが、むしろ活字人間としては近代の印刷とは何を抽出した(捨象した)かが知られる所に興味が湧く。
オング説を批判して曰く、「言葉をものに変えるのは視覚ではない。言葉が書かれるのではなく印刷されるとき、文字生産物からそれに技術的影響を与える身体動作が断ち切られることによって、言葉はものに変わるのである」(p.58)。「つまり刻印[engraving]という技法こそが、身ぶりと軌跡とのつながりを断ち切り、文字や漢字を不動のものとし、そうすることで、言葉とは技術によって組み立てられ配置されるが書き込まれるものではない、という今日の認識の礎を築いたのである」(p.214)。……「図示表現は、印刷された文字の連鎖のように辿るべき踏み跡をまったく残さないとき、どうして線状的になるのだろうか?[……]それはラインではないライン、すなわち点線という逆説である。点線が形成されるときには、まず元の軌跡が切片に分断され、次に各の切片が点に圧縮されるという過程を思い出してほしい。線状化の過程の本質とは、まさにこうした断片化と圧縮――〈運び〉の流れる動きの瞬間の連鎖への縮約――にある」(p.230)。
言葉の記述と音楽(歌)の記譜とが未分化だった古典古代期において文字に附加されたアクセント記号である「ネウマ」の例(pp.46-47)は、日本語声調史の資料とされる声点との類似を感じさせた(読んだばかりの小松英雄『国語史学基礎論』からの聯想)。「現代の楽譜においてかつてのネウマは洗練を極め、当初の言葉との結びつきから離れたシステムを形成した。それと対照的に、文字記述物[script]の場合、現在ネウマは句読点の姿でかろうじてシステムの隙間に生き延びているに過ぎない」(pp.50-51)。「句読法の起源はネウマの場合と同様にすでに書かれた写本へのマーキングであり、演説者が吟唱あるいは朗詠するテクストを上手に区切って表現するための補助であった」(p.51)……。連なる線を句切る分節と、身体性からの疎隔と。
「印刷されたテクストは、苦労してそれを生みだした人々の活動の痕跡を残してはおらず、あらかじめ組み立てられた制作物ないし作品としてあらわれる」(p.53)。「記述[かくこと]の終焉は、表面[surface]の知覚の根本的変化によって宣告されたと私は確信している。つまり、表面は今やそこを通ってそこを通って進む領域のようなものから、それを眺めるスクリーンのようなものへの変化し、その上に他の世界からやってくるイメージが投影されるということになったのだ」(p.54)。「手の身ぶりと文字の刻印との緊密な結びつきを破壊したのは印刷術であった。だが印刷がいま問題にしている知覚の変化の原因だったと主張することはためらわれる。なぜなら多くの分野で――たとえば工学や建築において――印刷術に匹敵するさまざまな発展が同時進行していたからである。[……]つまり熟達した手仕事が「想像力に満ちた」デザインや構成と「単なる」技術行使という別々の要素に分離され、それによって肉体労働――印刷工や大工や機械工の――は、機械でも十分こなせそうな、あらかじめ決められた一連の操作の実行へと格下げされてしまったからである」(p.54-55)。
ここで、書物史に関心する読者なら、ふと、カルロ・ギンズブルグ「徴候――推論的範例の根源」のくだりが聯想されてもよい。ギンズブルグはジャック・グディ著等を註に挙げつつ言ふ、「事実、文献学の対象となるテキストは、固有の特徴を大幅に捨て去ることによって(この除去の幅は後には小さくなるよう定められてはいたが)作られたのである。[……]初めは朗唱及び仕種に関する要素はすべて、テキストに関連しないとみなされた。そして後には筆記形態もそうみなされるようになった。この二重の操作の結果として、テキストは感覚でとらえうるあらゆる要素を除去され、徐々に物質的性格を失うことになった。」「テキスト・クリティックはある決然たる決意のもとに、テキストのもつ再現可能な部分(初めは手写で可能な部分、グーテンベルク 以降は機械的に可能な部分)だけを考慮するようになった」(竹山博英訳『神話・寓意・徴候』せりか書房、一九八八年十月、pp.196-197)。或いはまた、ミシェル・フーコー『言葉と物』の一節を想起してもよい。第五章「三 構造」に曰く、博物学等に顕著な通り十七世紀以降「視覚に、ほとんど独占的な特権があたえられる」……「すなわちそれは、他のあらゆる感覚的要素を奪われ、そのうえ灰色の単彩画に変えられてしまった可視性なのだ」(渡辺一民・佐々木明訳、新潮社、一九七四年旧版p.156)。これは佐藤健二『読書空間の近代 方法としての柳田国男』第1章7(弘文堂、一九八七年十一月、pp.60-61)が引いて論じた所でもある。
嶋崎正樹評「でも、どこかノスタルジックに(?)身体性や身振りを言いつのるよりも、そうした新しい布置の中に、古くからの身体性を改めてどう位置づけるか、あるいはどう位置づけてきたのかを問うほうが、よほど建設的だし重要だ。」(『Silva Speculationis ―思索の森』2014 年 6 月 10 日)
http://www.medieviste.org/?p=7288
森洋介
1971年東京生まれだが、転勤族の子で故郷無し。大学卒業後、2000年まで4年間ほど出版編集勤務も(皓星社含む)。2004年より大学院で日本近代文学(評論・随筆・雑文)を専攻、研究職には就かず。趣味は古本漁り。関心事は、書誌学+思想史(広義の)、特に日本近代で――それと言葉。業績一覧はリサーチマップ参照(https://researchmap.jp/bookish)。ウェブ・サイトは「【書庫】或いは、集藏體 archive」。
■書物蔵からひと言
今回も高度に抽象的な話を、抽象的にディスクリプト(記述)してますなぁ……。
石であれ紙であれ、文字を手でライト(書記)する場合には、どうしたって線を引いていかねばなりませぬ。ところが活字が開発されると、それペッタン、と、刻印することになりまする。すると、手書きをする際の、体のうごきとは全然ちがう動きなので、心にもっと抽象的に感じられる、ってな話をしているように見受けられます。
つまり、活字で見たほうが、手書き文字で見た場合より、より言葉が抽象的に天から降ってきたように感じられるのではないか、とインゴルドは言っているようである。
テキストを比較する、というのは、書き手の筆跡や書風を捨てて――つまり「捨象して」――抽象的な、そう活字的なものとして並べることで初めて本文校訂がスイスイできるというわけで。
そういったことを森さんはインゴルド著から読み取り、日本的な「心でっかち」を戒め、近代的「頭でっかち」を勧めているように見受けられる。いやはや賛成なり。
友人代表・書物蔵識
(Twitter:@shomotsubugyo)
☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。