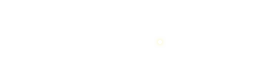第1回 宮崎芳三, 水越久哉『イギリス文学者論』は出版史、読書史でもある――「読書公衆」の初出はコールリッジ?
■口上 正直森さんの本の本、学問史本の辛口書評
市隠。私が勝手に市井に隠れているとみなしている友人の森洋介さんは、私の古本フレンズたる恩師が「博覧強記」と評した人。少なくとも学問史や本の本について、彼のアドバイスを聞いて損したことがなかったのは、知友になってここ16年ほどの事実である。
そこで今回、彼を皓星社メルマガに引っ張り出したいと思ったのだが、この御仁、締切りを破ることにかけては実績がありまくる。そこで〈既に書いたもの〉なら、さすが締め切りを破れないだろうと、過去に書いた学問史や本の本についてのメモを出してもらった。
多くは断片のメモなのだが、そのうちから私が勝手に「これはオモシロ」と思ったものを随時、連載としてここに掲げて行きたいと思う。
ところで、森さんは旧字旧かな主義者なれど、それはニワカ右翼・保守主義より来るものではなく、むしろ合理主義の発露である。ここに転載するにあたっては、新・旧漢字は新漢字に寄せて、かなは旧かなのママとすることにした。新旧字を新字に寄せるのは、ひとえに現行システム下で、取次たる私が全部正しい旧漢字に寄せることができないからである。但し複数の別字が一つの新字に統一されて一対一対応しない場合は正字で表記した。
とりあえず初回は英文学者が書いた「本の本」。
友人代表・書物蔵識
(Twitter:@shomotsubugyo)
■宮崎芳三・水越久哉『イギリス文学者論 過渡期としての第18世紀』〈松蔭学術研究叢書〉松蔭女子学院大学・松蔭女子学院短期大学学術研究会、一九九一年三月
読了 2017/01/14
見返しに献呈署名「岡照雄様/敬意をこめて/1991年5月 宮崎芳三」。
宮崎芳三は、共編の『日本における英国小説研究書誌』を別にすると、好著『太平洋戦争と英文学者』(一九九九年)はあるものの、退官を機にした私家版三百部と聞く『文集』三巻(一九八八年~)以外、本書にしか研究論文を纏めてゐない(谷沢永一「『日本における英国小説研究書誌』」『書誌学的思考』〈日本近代文学研叢〉和泉書院、一九九六年一月、p.572)。研究者としての評価は本書に就くべし。
本書の内容は、小林章夫『大英帝国のパトロンたち』(一九九四年)p.196以下でも「なんだかそっけない書名だが、どうして中身は非常におもしろい」と紹介されてゐた。
第3章までは通説である十八世紀イギリスにおける文学者人口増加を計量書誌学風に裏づけてゆく作業だから退屈になりさうなものだが、術語や概念を用ゐないエッセイ調の悠揚迫らぬ文章で述べられて、常識を尊ぶイギリス流アマチュアリズムを身に体するが如くである。統計技術の専門家からは素朴に過ぎると難じられるかもしれぬ。巻末「注」から窺はれる通り既発表論文を縮約しつつ纏めた本ではあるも、平語を以てする餘裕ある話法ながらやや冗漫の感あり、今少し切り詰めた行論の方が要点は明確になったらう。
書名に「文学者」と言っても「詩人」「劇作家」「小説家」以外に「ジャーナリスト」を含むのが興味あるところ。特に「第6章 ジャーナリスト再論」。フリート街グラブ街の三文文士、「miscellaneous writer」(p.169、雑文家)ども……。だが彼らは意外に高学歴であったと判明する。また出身を分析して曰く、「こんなにもさまざまな職種の人たちであふれているこの世界になぜ軍人と商人がいないのだろう」――「たぶん軍事や商売は、文字通りに実行の世界の仕事で、軍人や商人は、聖職者、政治家、まして文学者のように、口八丁である必要はなかったからであろう」(p.173)。他方、実践に縁遠いのみならず言論からも遠ざけられた層があった。同章最終節に曰く、「第18世紀ジャーナリズムの世界は男性オンリーの世界であった、と言っておく。」「この章で先に私たちは、当時女性は公の社会生活からしめ出されていた、と指摘した。政治、経済、軍事、信仰のすべての面にわたって、それらを受け持つ公の活動から彼女らはしめ出されていた。そして、ジャーナリズムとは、それらの公の活動を話題にして扱うことがその任務であるから、その活動そのものにかかわらない女性がジャーナリズムにもかかわりをもたなかったのは、少しも不自然でない」(pp.187-188)。なればこそ、婦女子は「そういう者として、その公の生活から洩れているもの、それからしめ出され、とじこめられているもの、すなわち個人ひとりひとりの感情を扱った物語を、もとめた」(p.182)のであり、それは小説といふ新しき革袋に盛られ、そして「この世紀、小説が歓迎されたのと平行して、悪口をあびせられ」「とくに商人の側から小説に対する手きびしい悪口が言われたという事実」は「女性とは違って、あいかわらず公の活動に多忙な男性としては、表の生活からしめ出していたものをこそテーマとした物語というものは、ちょうど社会生活から女性をしめ出しているのとまったく同じ扱いを受けるのが当然のものであった」と見れば釈然と解ける(p.182)……。ここで、公共性(publicness)と私秘性(privacy)の対立概念で括るやうな論述は出て来ないし、同世紀における文学史上の所謂センチメンタリズム(感傷主義)にすら論及されない。
ちなみに、「読者層(reading public)という言葉を最初に使ったのは(私たちの知る限り)S. T. Coleridgeかもしれない」(第4章第4節注(59)p.197)とのこと。reading publicは読書界とか読者公衆と訳したい。元来「ペイトロン制度(patronage)」(p.123)下では「共通の文学感覚をもっていた」「公衆」(p.126)の連帯感に基づいて「既知の特定少数者」(p.130)が読者に想定されたが、そのやうな「意識の共同体」(p.130、ボズウェルより引くジョンソンの言)に代って世紀後半には「出版者という商人」(p.131)「自由競争の原則にのっとった出版市場」(p.135)を介した「不特定多数の未知の読者」(p.131)が「「作品の受け手」というバトンを受けついだのである」(p.136)。
「第4章 文壇の状況」から総論に入り文学者人口の調査結果に就てその意味を説くが、半ば出版史ともなってをり、まづ新聞雑誌の隆盛を世紀間を通した発行点数調べと共に考證し、次いで著作権成立やドナルドソン事件やラキントンによる廉価販売等の叙述を含む。また読者論でもあり、女性比率への注目から、名高いイアン・ワット『小説の勃興』(鳳書房、一九九八年/南雲堂、一九九九年)に対しても附論となる「第5章 女性作家の登場」以降で批判を提出する(p.152・161・179・182)。
「私たちは、文学者の思想の力で歴史が変っていった、とは考えていない。第18世紀当時の小説家が、個人主義思想(それがどんなものかはワットの本にくわしく書いてある)を思いつき、それを信じ、異なる思想の持ち主と対抗し、彼らと戦い、その戦いに勝つ――という形で当時の文学の歴史がすすんでいったとは私たちは考えていない。その逆に、むしろ文学者は(詩人も小説家も)あまり変りたくはなかったのだ、と考える。そしてもしも彼らが変っていったとすれば――たしかに変った、その点についてはもう少しあとで触れる――それはじつは変らされた、と言うべきで、し方なしに変っていったのだ、と私たちは見る。彼らの変化は、外からの力、すなわち外部の諸条件の変化が彼らに強いてくる力、のせいである。その外部の条件とは、一口で言えば、活字印刷による文字情報――文学とはまさにそれである――の流通のしくみにかんすることである」(「第5章 女性作家の登場」p.161)。これを約めてメディアといふ概念を出して説くことはなされない。飽くまで経験論的な次元に留まりつつ考察が進められる。
森洋介
1971年東京生まれだが、転勤族の子で故郷無し。大学卒業後、2000年まで4年間ほど出版編集勤務も(皓星社含む)。2004年より大学院で日本近代文学(評論・随筆・雑文)を専攻、研究職には就かず。趣味は古本漁り。関心事は、書誌学+思想史(広義の)、特に日本近代で――それと言葉。業績一覧はリサーチマップ参照(https://researchmap.jp/bookish)。ウェブ・サイトは「【書庫】或いは、集藏體 archive」。
■書物蔵からひと言
この書評を読んで、あわててサイト「日本の古本屋」から注文した。文学はあまり読まないが読書の歴史に興味があり、それも、読書公衆(reading public。このコトバは読者公衆とも読書界とも訳される)に興味があるので、この語の初出を解説する日本書があるとは知らなかった。
宮崎芳三は2010年に『太平洋戦争と英文学者』(研究社出版, 1999)を森さんに勧められて古本で購入した際に(拙ブログ参照:https://shomotsugura.hatenablog.com/entry/20101105/p3)、その一種独特のオモシロさは知っていたので、一も二もなく注文したのであった。
☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。