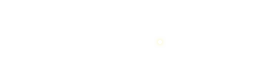第22回 特別編・『近代出版研究』第2号の編集余話
河原努(皓星社・近代出版研究所)
■なんで雑誌を編集しているのだろう?
来月上旬、近代出版研究所の年刊研究誌『近代出版研究』第2号が発売になります【図1】。元々がレファレンス・ツール屋――それも人物データベース屋――なので「なんで雑誌編集――まあ実際は論文集の編集なんだろうけど――をしているんだろう?」と思いつつ、半年以上にわたって編集作業をやってきた訳です。
最初に「だいたいこれくらいの文字数が望ましいのですが……」とお願いした結果が2倍3倍になったり(内容良ければ全て良し!)、「別件を優先しなければいけないので、今回は落とさせてください」と言われていた方から「片付いたので短いものなら書けますよ」と無事ご寄稿を頂けた一方、やっぱり別のお仕事の合間に「なんとか書きたい」とギリギリまで粘って頂いたけれど「申し訳ない!」と間に合わない方がいらっしゃったり。そこら辺は具体的には書けませんが、今回は発売前に少しでも弊誌に興味を持って頂けたらと、2つの編集余話をご紹介します。
ちなみに「日本の古本屋」メールマガジンの2023年4月25日号に、小林昌樹編集長が弊誌について書く予定になっておりますので、そちらもお楽しみに。
【図1】今回も自信作です

■横山茂雄ロングインタビュー余話
横山先生にお話を伺うのは、近代出版研究所員である森洋介さんの発案。インタビューは夏の終わり、2022年8月下旬に行った。横山先生と菊地暁さんはオンラインでの参加だが、神保町のオタさんや志村真幸さんはわざわざ弊社までお越しくださった。話は大変に盛り上がったものの、諸事情により2時間で中断せざるを得ず、やむなく9月初旬に追加の第2回インタビューを行った。第1回ほど時系列に沿った話にはならなかったが、それを上回る3時間の長丁場になり、合計5時間の録音が残された。
文字起こしアプリで粗起こししたテキストを、録音を聞きながら整理していく。結果、第1回の内容はほぼ全て採用し、第2回からは前回の補足になる箇所や特に面白い話を拾い上げて追加した。カットするには惜しい話が多く、あれもこれもと欲張ったら、4万字(!)というロングインタビューになってしまった。泣く泣くカットしたものには、例えばこんな話も。
横:菊地さんのご本(『民俗学入門』岩波新書、2022)、奥付に身長が入っているよね。
菊:そうです。編集者に入れさせられました。
横:あれは自分の意思じゃないの? 菊地さんはアンドレ・ザ・ジャイアント(※1)くらい大きいんですか(笑)。
菊:186センチなので、そこまで大きくはないです(笑)。
横:菊地さんに張り合うわけじゃないけど、僕も本邦近代出版史上唯一でないかという奥付を作ったことがあるんです。一般に流布している書籍の奥付を自分の手書き文字で記しています。孔版刷りの雑誌や本じゃないからね。
一同:へえー。
河:何というタイトルの本ですか?
横:国書刊行会から出ている、マーヴィン・ピーク『行方不明のヘンテコな伯父さんからボクがもらった手紙』(2000)です。ピークという人は画家が本業なんですけど物語も書いていて、この本の原書は絵、タイプライターで打った文字、そして手書きの文字が混在した形式です。 だから、翻訳に際しては、ピークによる手書き文字の部分はすべて僕の手書き文字に置き換えた。原書のコロフォンも手書き文字だったので、翻訳の奥付も僕の手書き文字。普通の書籍で、奥付が手書き文字というのは本邦近代ではこれだけじゃないですかね(笑)。
一同:ハハハ。
小:それは一冊一冊、手で書き込んだんですか?
森:それは無理だよ。何百冊ならともかく。
横:奥付というのは出版物にとって重要な箇所で、そこが手書き文字というのは非常に珍しいでしょう。反響を呼ぶかなと思ったけど、誰も驚いてくれなかったみたいだね。
※1 戦後に活躍したフランス出身の巨漢プロレスラー。身長223センチ、体重230キロで、プロレス実況の古舘伊知郎が付けた“人間山脈”“一人民族大移動”の異名は有名
これはパソコンを介したインタビューなので「ディスプレイに映る先生の姿を撮ってもなあ……」と思い、その場の写真は撮らなかった。しかし原稿を整理するうち「やっぱり撮っておけばよかったかな」と考えていたら、ちょうどオタさんから「(古本市で)横山さんに出会って写真を撮らせてもらいました。うまく撮れませんでしたが、『近代出版研究』に使えるようでしたらお使いください」と数枚の写真が送られてきた。「おお、これだ」とさっそく冒頭部分に挿入して初校を送ったのだった。すると、横山先生からこんなメールが。
河原 さま
インタヴュー初校ゲラ、昨日届きました。
冒頭の写真、いかにも怪しげな爺さんが映っており驚く。当方の人品について(さらなる)誤解が広まるのではないかと…。
追伸
犬好きの好々爺?として映っているはずの写真を添付しておきます(犬はアラスカン・マラミュート、4歳メス。これが家の中を徘徊しています)。
せっかくなので、本編に挿入できなかった好々爺の写真を公開させてもらう許可を得ました【図2】。
【図2】

■稲岡勝「雑誌屋考」余話
本誌に「雑誌屋考」をご寄稿いただいた恩師の稲岡勝先生は、来月で80歳になられる。私とは35歳差で、初めて出会った時は20歳と55歳。先生はいまの小林編集長くらいの年齢であった(のだなあ)。いまもお元気な先生だが、オーラルヒストリーの適齢期(?)は70代と耳にしたので、昨年の初夏に『近代出版研究』とは別に、小林・森・河原の3人で先生に研究史について伺った。その折「部屋を整理していたら、こんなのが出てきたよ」と見せられたのは、日本エディター・スクール出版部から1990年代に出るはずだった書籍の企画書。伊藤隆監修、百瀬孝著『事典 昭和戦前期の日本―制度と実態』(吉川弘文館、1990年)の出版史版を企図していたそうで、何人かの専門家と定期的に集まりを持っていたとのこと。『近代出版研究』第2号には、この企画書を転載して、当時の思い出を書いて頂くことにした。しかし、興が乗らなかったのか、定期的にご機嫌伺いのお電話を差し上げても「うーん」という感じであった。
12月に入って、私に手紙が届いた。先生のゼミ生で、私の妻と同期の女性からだ。数ヶ月前に弊社の出版目録を作った際に彼女にも送ったので、その礼状だった。読み進めていくと、大病を得たこと、そして「主治医から「命に係る事態が数ヶ月、早ければ年内に」と言われて」いるとあり、粛然とした気分になった。すぐにでもお見舞いに行きたいが、ホームページで確認すると病院はコロナ禍により面会謝絶の様子。やむを得ず手紙を出すことにして「お見舞いにいけないのは大変に残念です」と記し、先生や彼女と東京見物をしていた当時の写真を同封して速達で送った。
数日後、彼女の配偶者から「是非、先生にお見舞いに来て頂けないか」との手紙が届き、すぐ先生にお電話を差し上げた。私も同行したかったが、ちょうど担当した『調べる技術』の発売日前後で、身動きが出来ない時期であった。翌日の夜には先生からお電話があり、昨日の今日ですぐにお見舞いにいったこと、彼女と会えたことを教えられた。ホッとしたのもつかの間、翌週の打ち合わせ中に先生からお電話があった。この時間に先生から連絡があるということは……と打ち合わせの後で折り返すと、やはり彼女の訃報であった。自分より若い友人を初めて亡くしたので、言葉がでなかった。
それからしばらくして、先生から新しいテーマで原稿を書き始めたことを教えられ、無事に初校を頂いた。お電話を差し上げると「実は彼女のことを思うと、もう少しやらなければならないと奮い立たされたんだよ。それでページに余裕があれば、少し彼女にふれてそのことを書こうと思うんだ」と仰り、私も「ひっそり彼女の名前を記して、私たち2人だけがわかる紙碑にしましょう」と話したものの、再校ゲラを反映するとページがちょうど埋まってしまったので、その文章を挿入できなかった。この稿を草するに当たって先生にお電話を差し上げたら、改めて次の文章が届いた。
「四重の五重の重箱みたいに歳ばかり重ねて」、たちまち古稀をすぎて傘寿に。年は簡単にとれる。日々無為に過ごすことはもっと簡単だ。後期高齢者ともなると、持病のグータラ病はさらに亢進する。近代出版史の構想は枯野を駆け巡っても、物憂くて机に向かう気力がわかずに夢と化す。こうして今年も「看又過」(みすみすまた過ぐ)のかと思っていた。
そんな折、昨年十二月初旬に河原の元へ都留時代の旧ゼミ生から手紙が届いた。東京のあちこちを歩いた時の楽しい思い出が綴られていた由。東京で職を得た旧ゼミ生有志を集めて、確かに食べ歩きや文学散歩らしきことはやっていた。
しかし差出し人の住所が、柏市の「国立がん研究センター東病院緩和病棟内」と知って暗然とした。彼女はもう長くはないと覚悟して最後の挨拶を送って来たのに違いない。病院での見舞いは不許可ゆえ、とりあえず河原が昔のスナップ写真を添えて見舞状を送った。
ほどなく夫君から病院を出て自宅で緩和ケアしていること、できれば見舞って欲しい旨電話があった。意識のハッキリしているうちにとすぐに出向くことにした。見晴らしの良い最上階の部屋で、彼女は大切な人に囲まれて尊厳ある死を迎えようとしていた。病苦のやつれも余りなく手を握り呼びかけると、かすかな反応があった気がした。聞けば十九年に発症手術して以来、ちょうどコロナ禍騒ぎの期間中二人して闘病生活を送って来たのである。重い現実に言葉などは軽すぎて何も言う気になれなかった。
それから四日後(十二月十三日)夫君から、眠るように息をひきとったとの電話を貰った。見舞いは辛うじて間に合ってよかったが、八十年の半ばであの世に旅立った彼女と夫君の喪失感のことを思うと気持は重く沈むばかり。ただこの厳粛な事実は宿痾の怠け病を吹き飛ばしてくれた。抵抗もなく進んでパソコンに向かい、中断していた課題「雑誌屋考」と取り組み、『近代出版研究』2号に寄稿することが出来たのは幸甚であった。
きわめてパーソナルなことではあるが、河原夫妻(夫人はゼミの同期)ともども共通の友の死を追悼し、あわせて忘れ得ぬ人の記憶を文字にとどめるためにこの一文を草した。
二〇二三年三月 稲岡勝
彼女と最後に会ったのは2012年、回数で言えば10回に満たない。けれども、恩師と妻との大切な想い出を共有する、淡いお付き合いながら、生涯忘れ得ぬ友人である。また、いつか、お会いしましょう。
☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。