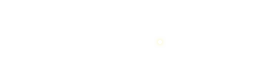番外編2 レファレンスの「暗黙知」を研究する最初の一歩は――『調べる技術』がヒットした原理的な理由
小林昌樹(図書館情報学研究者)
■レファレンスの神様、大串先生の講演は楽しい
国会図書館(NDL)関係者のツイートで、敬愛する大串夏身先生がNDLで講演するらしいとわかり、さっそく先生に連絡をとったところウェルカムとの返事をいただいたので、いそいそと出かけた。大串先生はレファレンス(調べもの相談)の数少ない専門家である。
私が先生をどれほど敬愛しているかというと、埋もれていた先生の名著『ある図書館相談係の日記:都立中央図書館相談係の記録』(日外アソシエーツ、平成6年)を、元版の版元違いの皓星社さんに頼み込んでわざわざ復刊してもらうほど、と言えばわかるかしら。ファンなので復刊にことよせて対談もお願いした(解説として復刊に収録)。
30年前の本だが現在でも価値があると、NDLに勤めていた頃の私が、復刊してもらい世に問うたというわけである。あえて言おう、閲覧系司書でこの本を読んだことのない司書はモグリであると。
・『レファレンスと図書館 ある図書館司書の日記』(皓星社、2019)

当日は、先生オハコの『国立国会図書館蔵書目録』を全部読む話――本当に読むのよ――や、1980年代、都立中央図書館におけるレファレンス方針の2つの方向性(文献調査重視派vs.事実調査も重視派)といった、面白くってタメになる話が続き、いつもながら先生の話は楽しいなぁと思いながら聞いたことだった。
最後に大串先生が「独学」などが社会でクローズアップされ(読書猿『独学大全』が26万部!)、そんななかで拙著『調べる技術』もこの手の本としては例外的に社会に受け入れられていると指摘(こちらは3万部)。国会図書館の調べる機能(特にレファレンス協同データベース)が社会的に大切と締めくくっておられた。
■拙著は横取り?!
それはよいのだが、質疑のところである国会図書館員が拙著『調べる技術』に言及し、これは館内掲示板(守秘義務に配慮し詳述は避ける)に載った他人のノウハウを横取りしたものだ、という趣旨のことを述べたので、心底驚いた。
その場で、「あれは頓挫した田村プロジェクトというものがあってだね、それはもともと認識すらされていない<暗黙知>を記述する研究で、認識されてもいなかったものをどうして横取りできるのだろう(いや、できない)」と反論しておいた。NDL館内にそんな意見があるのなら、とんでもない間違いだから拙著成立のウラ事情について説明しておく。ある種、NDLの「内輪の恥」をさらすことになってしまうが、やむを得ない。
■レファレンスの参与観察
田村プロジェクトとは図書館における司書のレファレンスプロセスをすべて記述するために、学者が文化人類学風に参与観察するというものであった。NDLでレファレンス質問を受けている人文課が、2017年ごろ学者先生をお呼びして、ベテラン司書、レファレンサーの暗黙知を研究する最初の一歩にしよう、というものであった。仮称のプロジェクト名は田村俊作先生(慶應義塾大学名誉教授)に由来する。
レファレンスがらみで利用者も司書も行っていることを、無意識的な所作も含めて記述し、回答につながる重要なプロセスをそこから抽出することが想定されていた。しかしこの研究プロジェクトは準備段階で頓挫した。
■十全な遂行知を持っていたレファレンサーはもっと上世代
ベテラン司書の「無意識」のなかには拙著の主要コンテンツ、リファーのノウハウもある。それを本当に持っていたのは私(1967-)なんかよりずっと上の世代だった。
名のあるところでは朝倉治彦(1924-2013)、稲村徹元(1928-、彼はNDLのいわば一期生)などに始まって、下ってはMさんやKさんなど、本物の「レファレンサー」の連中だ。しかし、彼らはみなとっくに退職して消えた。大串先生の話でも、当初(でもしか)司書っぽかった大串先生(1948-)を育てた人たち、つまり大正期生まれの存在がかいま見えたことだった。
コンピュータ、スマホのない時代、レファレンスツールは貧弱だったが、彼らベテランのレファレンサーにかかれば、難しい問題でも答えが出た。職人の神ワザ、神技である。
■人はどのようにして神になるのか――徒弟制
彼らはどうやって神ワザ的なベテラン職人となったか。運と努力とセンスによる、というときれいな表現だが、端的にいって徒弟奉公によってだった。たまたまレファレンス部門に入り込み(運)、職人的先輩に仕え(努力①)、ひたすらリファーの作業を繰り返し、ちまちまと主題書誌を作り続けた(努力②)からだ。センスは、努力①②の結果が良い場合、結果的に証明されるものだった。
■職人は有能だが弟子入りが難しい
1990年代半ばの飲み会で故・平野美惠子さん(最後のNDL図書館研究所所長)が「若い頃、わたしGRに行きたいですわって言ったら、十年早いと叱られたわよ!」と言っていた。「あの平野さんにしてからそうか……」と唖然としたのを憶えている。
いまでも厳然としてNDLの社会的威信を支えている調査及び立法考査局に対して、一般考査部「ジーアール(GR:general reference)」に巣食っていたレファ職人達。彼らはしかし、館内的には「うるさ型」と思われていた。図書館事業基本法案(1980年)に関わったNDLの名副館長・高橋徳太郎(1923-1997)が、細かく「欠本補充箋」を発出して収集担当に疎まれていた稲村徹元を擁護して、「朝倉さんや稲村くんのような<書物の魔>がNDLにいていいんだ」と言ったというが(稲村さんから直話)、この逸話は職人とジェネラリスト(事務員的気質の職員)との対立を象徴している。
■私のノウハウ仕入れ先
彼らホンモノは私がレファレンス部門に行った段階でほぼ現場から消えていたのでそもそも横取りは不可能である。
これは前著(『調べる技術』p.177)に書いたが、ではなぜ職人たちのノウハウを復活させられたのかと言えば、最後のホンモノに仕えた友人から<業務時間外に>いろいろ聞き出したからだ。横取りでなく、いわば「タテ取り」したようなものである。タテだから「継承」したともいえるし、制度外だから「密輸したんだ」などとよく冗談で言っている。
「として法」を思いついた事例(前著『調べる技術』p.137)は、その人を相談相手にしたものだ。いまも思い出す。難しいが有能なおばさま達と一緒に新館1F喫茶で昼食をとっていた彼の姿を。
2005年を境にNDL職員の館内喫茶文化は廃絶したが、この文化は徒弟制を補完する教育システムとして機能していた。喫茶文化は1980年代末に慶応大の図書館に勤めた際にも経験したことがあり、どうやら図書館界共通の文化だったようだ。
■徒弟段階で弾かれる人が……
本題の「内輪の恥」にもどそう。拙著のコンテンツたるノウハウの仕入れ先は他課の友人(職人の末裔)にあった。一方で拙著の全体コンセプトは田村プロジェクト由来なのだが、このプロジェクトが頓挫した主因は当時の部長の無理解だった。
レファレンス職人には徒弟奉公でなると言ったが、当然それだと弾かれる人が生じる。なんと間の悪いことだったろう、プロジェクトの企画時の部長が、若い頃、徒弟段階で弾かれた人だった。彼女は職人的な暗黙知をいかにして形式知にするか、という課題自体がわからなかった。
■職人ワザの継承と外部学者の視点で成り立った『調べる技術』
結局、プロジェクトは頓挫したが、先生の問題意識から、実はベテランのノウハウはほとんど意識化、言語化されていないということに私は気づいた(気づかせられた)。目に見えない<暗黙知>を素人は「ない」ものと考えがちである。そもそも気付かない。
今週もネットで「AIで司書不要」論者に対し、AIの回答からそれを否定するという荒業をしかけて成功していた読書猿さんが、対談※※でこんなことを言ってくれたのはさすが慧眼であった。
さらに、小林さんが稀有な存在であるのは、レファレンスのプロフェッショナルであると同時に、歴史の研究家でもあるという点です。この本には、ベテランの実務家が体得してきた現場の暗黙知と、それを一歩引いた目で見た抽象知が同居している。その点がとても面白く、他の本にはない魅力だと思います。
そもそも<調べる技術>などというものはどこかの館内に限定すべきものでもない。一種の公共財だが、みながいくら使っても枯渇も目減りもしない<情報財>なのだから、パブリックに知らせる(=パブリッシュする)べきものだ。
※※読書猿,小林昌樹「元国立国会図書館司書が書いた「調べもののバイブル」が飛ぶように売れている理由」『ダイヤモンド・オンライン』2023.1.2(https://diamond.jp/articles/-/315425)
小林昌樹(図書館情報学研究者)
1967年東京生まれ。1992年慶應義塾大学文学部卒業。同年国立国会図書館入館。2005年からレファレンス業務に従事。2021年退官し慶應義塾大学でレファレンスサービス論を講じる傍ら、近代出版研究所を設立して同所長。2022年同研究所から年刊研究誌『近代出版研究』を創刊。同年に刊行した『調べる技術』が好評を博し、2024年続編となる『もっと調べる技術』を刊行した。専門は図書館史、近代出版史、読書史。詳しくはリサーチマップを参照のこと。