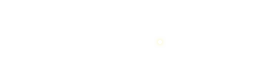第7回 純潔の詩
福島泰樹(歌人)
昭和23(1948)年5月、老いたピエロに身を俏した詩「ピエロ」で、「陽に熟れ」たようなデカダンスの心情を歌った延子は、6月になると大作「深夜の葡萄」を始め「追想」「乳房」「風車」「宿り木」「招待」「ランプ」「鎮魂曲」「白いランプ」「光」「ロバ」「生誕」と息も衝かせぬ勢いで12篇もの詩を一気に書き上げる。
この月、すなわち昭和23年6月13日には、作家太宰治が、戦争未亡人山崎富栄と玉川上水に入水している。太宰の死は、延子が在籍した県立桐生女子高等学校の教室(文芸部.社会部.新聞部)でも、大いに話題になったことであろう。一昨秋、土屋文明記念館で、太宰治展が開催され、そのいっかくに「夭折の詩人 長澤延子」のコーナーがもたれ、ツイッターに私はこんな投稿をしたことなどが思い出される。
太宰治自殺の翌年、17歳の少女が命を絶った。群馬県立土屋文明記念館「わらう!太宰治」展の一隅、『長澤延子全詩集』[皓星社]が積まれている。「あの子の体/飲んだゲキヤクで真青だよ」。2人の背後には戦争が黒い笑みを浮かべていた。《戦争が笑って手招きしていたよ銀紙あたまにのっけていたよ》
— 福島泰樹 (@yasukizekkyo) October 25, 2021
2人を結ぶものは、戦争であったのか。
そしていま一つ、道化……、とおい足音としての革命であった。
*
6月になって書かれた12篇の中に「乳房」がある。延子の詩に再会して以来、私が愛誦し続けてきた詩だ。15年前、私は、こんな風に綴った。
「私は、少女の潔癖を歌った、時代と自身の運命の予兆にあふれた、疼くように切なく可憐なこの詩が好きだ」。
この切ない官能の予兆と破滅に身悶える、韻律の震えと格調! これは黙読だけでは味わい切れるものではない。どうかいくたびとなく唇にのせ、自身の声で、(延子調に言うなら)味わってもらえまいか。これは唇を震わせて、格調高く歌い上げる純潔の詩なのである。
「乳房」全編を引く。
白い乳房のひそやかにうずく
初夏の胸寒い夜幼ない指で若さをかぞえて見る
あゝ遠い荒原に足音がきこえもたらされるものは
甘いやさしい夢ではない私はシャツの暖かみから
乳房を離して
あらわな白い塊に
遠いひゞきをしみこませるのだやがて風の訪れに
——私の乳房は
血に染んでたおれるだろうそれでもいゝ
暗い荒原の風をおもいながら
ゆれ動く乳房はかすかにうずき
今宵 ものかげを離れようとする
この詩を読む度に思う。詩は、解釈するものではない。感受するものである。感受さえすればよいのだ、意味内容はおのずとあとからついてくる。深く感受するためには、その調べを諳誦し続ければよいのである。それはやがて、自身の血肉となり、自身の詩になってゆくことだろう。私が、朗読にこだわり続ける理由である。
ところで16歳の魂は、この赤裸で官能的でさえある詩を書くことによって何を得、何を喪ったのか。何を象徴し、何を捨象したのか。
*
もう一度、唇にのせてみよう。(唇にのせる? そう、「唇にのせる」は私の造語であるのかもしれない。発声してみようの意だ)
白い乳房のひそやかにうずく
初夏の胸寒い夜
この赤裸でしかも美しい、官能の発露に私はたじろぐ。しかも「初夏」には「はつなつ」のルビではなく、あくまでも現実を想起させる「ハツナツ」のルビ。
幼い指で若さをかぞえて見る
あゝ遠い荒原に足音がきこえ
指にまとわりつく憶い出を打ち消すように、はるか荒原から足おとが聴こえてくるのだ。それは死の誘いであろうか。
もたらされるものは
甘いやさしい夢ではない
死への誘い、そんなあまやかな夢などではない。
その足音は、戦争で死んでいった人々があげる破産した夢の数々、あゝきたるべき革命の予兆にみちた、かすかな足音であるのかもしれない。
私はシャツの暖かみから
乳房を離して
あらわな白い塊に
遠いひゞきをしみこませるのだ
官能と純潔、肉体と精神、この相克と葛藤の中に乳房はかすかに疼き揺れうごくのだ。
*
この詩を書いた半年後、延子は10連71行からなる詩「アカツキ」を、まるで泥水を吐き出すように書きなぐり、「かすかな足音が階段を登る」と書き記すのである。そして、革命の幻想に無惨にも打ち砕かれた自身を、「アカツキ/私は目を開く/お前めくらでびっこの娘よ」と蔑み、「ころがりまろび お前 走り行く/お前 めくらでびっこの娘」と哀れむのである。
春になって自殺に失敗した延子は、「アカツキ」を巻頭にした「手記」を、ノートに書き連ねてゆくのである。
コムミュニズムは私が社会を恋しぬくためのひとつの契機だった。 『手記「A」』
肉体にも精神がある、
それが肉体だ。
私はこのきびしい事実にだけ生きたかったのだ。 『手記「A」』
疲れのために自失しようとする魂を、(略)青空の彼方に私の実在感を吸いこませることによって保って来た。 『手記「B」』
魂の破滅を自らの破滅となすことによって肉体は自身の誇りを保たなければならないのだ。 『手記「B」』
私にまつわって離れず常に力ある限りのたゝかいを要求したのは、
民衆とゆう課題だった。
民衆の魂と生活の現実とその将来の良心だった。 『手記「B」』
これらの断片を想起しながら、もう一度「乳房」を読み返してみるなら、おのずと16歳の少女が、いな、詩人長澤延子が、身を賭して歌わんとする意味内容は了解されるであろう。
そう、「暗い荒原の風をおもいながら/ゆれ動く乳房はかすかにうずき/今宵 ものかげを離れようとする」のである。
福島泰樹(ふくしま・やすき)
1943年3月、東京下谷生。早大卒、69年、歌集『
☆本記事は皓星社メールマガジンにて配信されました。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。