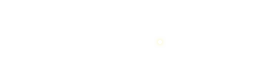福島泰樹(歌人)
「うき雲」で延子はこう歌った。
「あゝ私はまだ/こんなに若いのになあ/ポカリポカリと何処へ行く 雲よーー」
この虚無感はなんだろう。
15歳の少女はまた、空を見上げる。
また心は平穏を失った
吸いつけられたように
仰ぐ大空に雲は行く 「雲」
「うき雲」に続く詩は「雲」だ。
「吸いつけられたように」の語が、私に啄木の歌を思い出させる。
不来方のお城の草に寝ころびて
空に吸われし
十五の心
後年、東京にあって「十五の心」のありさまを回顧した作だ。
ところで、延子の「吸いつけられるように」大空を仰ぐ心の在りさまと、啄木の「空に吸わ」れてゆく心の在りさまは異なる。
「雲」2連目を引く。
かすかに あやふやに
保っていた心の光は
昨日 あの一言で靑空にのがれ出た 「雲」
かろうじて平穏を保っていた「心の光」は、青空へと逃れ出るのである。吸収されてゆくのではない、脱走してゆくのである。
「十五」の啄木の心は、ひたすらに空に吸収されることを希った。それは未来へ羽ばたいてゆく夢であり、身を焦がすような熱い期待ゆえであった。しかし、延子は、きれいさっぱりと未来を遮断してしまった。そして、呻くように「フルサトよ」と叫ぶのである。
故郷ならざる、フルサト……と。
3連、4連、5連を引く。
フルサトよ フルサトよ
お前の中で生れ育った
この魂のどこに……
どこに反逆の心を生みつけたのか
フルサトよ フルサトよ
私はお前から逃れ出たいのだ
靑空に雲は行く
フルサトの上 雲は光る 「雲」
啄木にあって故郷は、「逃れ出」る対象であったことには間違いない。啄木の行手には、文学があり東京があったからだ。しかし、夢破れて、敗残の身を養う場所はあくまでも故郷渋民であったのだ。よしんば、「石をもて追はるるごとく/ふるさとを出でしかなしみ/消ゆる時なし」と一家離散の悲しみを歌おうとも、帰るべきところは常に故郷の山河を置いてほかになかった。
病のごと
思郷のこころ湧く日なり
目にあおぞらの煙かなしも
小説では「雲は天才である」と謳ってみせた啄木であったが、延子のように「雲」を歌おうとはしなかったのはなぜか。「竜のごとくむなしき空に躍り出でて/消えゆく煙/見れば飽かなく」。「雲」は、自然現象であり、「雲」には人為が加わらないからであろうか。しかし「煙」はそうではない。「青空に消えゆく煙/さびしくも消えゆく煙/われに似るかな」。目に映るのはつねに、青空にたちのぼり、夢破れてはかなく消えてゆく一すじの煙であったのだ。
どうしたのだろう。一連三行の「雲」が三行書きの啄木の歌を呼び起こしたのか。そうではない。延子の詩の根底に「思郷」の悲しみを、遮断しえない「望郷」の想いを見てしまったからであろう。
6、7連を引く。
夜になってあの空に
クリスマスのような
星が輝いたとて
どうになろう外套の衿を立て
暗い路次をさまよう
私に帰る家はない 「雲」
「帰る家はない」だと……。だが、延子は、事実、実際のことを言っているのではない、そんなことは百も承知で、こう問うてみたくなるのだ。
あなたには、恵まれた養家の家があり、実家には、血を分けた父と兄、姉もいるではないか。敗戦から2年目、祖母に手を引かれ歩いた上野駅周辺の4歳の記憶が不意に蘇えってくる。
構内も地下道も戦争で帰る家をなくした浮浪者であふれるばかりだった。家を焼かれ、肉親と死に別れた半裸の子供たちが、浮浪児に身をやつし、盗みかっぱらい、モク拾いを生業としてまでも、必死に生きようとしていた。夜空に輝く星は、けっしてクリスマスのようには見えはしなかったであろう。
延子もまた、そんなことは百も承知で歌っているのだ。
啄木をむしかえすなら、啄木との決定的違いは、啄木は、間近の死を自らに命じてはいなかった、ということだ。だから心を素直に空に遊ばせることができたのだ。延子は常に、自らの決断で可能な間近の死を抱ながら、詩に真向かっていた。8、9連を引く。
大空に雲は行き
私はそれを見る
灰色の地球上
反逆と自由は
千切れるように雲を呼ぶ 「雲」
「灰色の地球上」という措辞が、この詩では浮いているように思われてならない。しかし、あの時代、私ら幼友達の間では、「地球上」は親密な言葉であった。昭和22年、焼跡にバラックが建ち東京の町々は復興した。家々の窓からはラジオの、笠木シヅ子が唱う「東京ブギウギ」の声声が流れ、川田晴久が唱う「地球の上に朝が来る」が希望をがなりたてるように陽気な歌声をひびかせていた。「〽︎地球の上に朝が来る/その裏側は夜だろう/犬が西むきゃ尾は東……」
あの時代の記憶の体験が、延子の詩にリアリティーを与えてゆく。
とまれ、決断によってもたらされる「間近の死」に替わるイデオロギーと、やがて延子は出会うことになるのだ。15歳の瞳が直視した「千切れるような雲」が、ほどなく「反逆と自由」を呼ぶのである。
やがて延子の意識は、戦争で夫を喪い、父を喪い、家をなくした子供たちに接近してゆく。矛盾するようであるが、詩を書くという行為が、そうさせ、またそうさせまいとしていったのかもしれない。
「雲」終連の詩句を引く。
影はるか フルサトを
雲は光り 雲は光り
大空に 白く行く 「雲」
反逆と自由の千切れそうな想いの「影」のはるか、フルサトの上空を「雲は光り」「白く行く」のである。
*
生涯の友となる女学校(桐生女子高等学校)1年後輩の高村瑛子と文通を開始したのは、「雲」をなした昭和22年11月であった。しかし「Tへの手紙」(『友よ 私が死んだからとて』天声出版、1968年刊)第一通には、「雲」の重苦しい葛藤はない。手紙から、この頃延子が、尾崎秀実の獄中書簡集『愛情は降る星のごとく』、エドガー・アラン・ポー短編集『あひびき』(出水書園)、アンドレジード『女の学校』『狭き門』などを読んだことが知られる。
延子は、魂のよき語り手を持ったのである。15歳最後の詩は、昭和23年1月に書かれる「雲」同様、1連3行を多用した「離愁」である。延子は文語体5音、7音の華麗な使い手でもあったのか。
終り2連を引く。延子における「雲」を思う。
眞白き雲に
君 忘れむ
その果を追えど
ーー眞白き雲に
君 忘れ得ず
その果に行く 「離愁」
福島泰樹(ふくしま・やすき)
1943年3月、東京下谷生。早大卒、69年、歌集『バリケード・一九六六年二月』でデビュー。「短歌絶叫コンサート」を創出、朗読ブームの火付け役を果たす。85年4月、「死者との共闘」を求めて東京吉祥寺「曼荼羅」で「月例」コンサートを開始。ブルガリアを皮切りに世界の各地で公演。国内外1700ステージをこなす。単行歌集に『下谷風煙録』(皓星社)他33冊、全歌集に『福島泰樹全歌集』(河出書房新社)。評論集に『弔いーー死に臨むこころ』(ちくま新書)『寺山修司/死と生の履歴書』(彩流社)、『誰も語らなかった中原中也』(PHP新書)、『追憶の風景』(晶文社)。他にDVD『福島泰樹短歌絶叫コンサート総集編/遙かなる友へ』(クエスト)など著作多数。毎月10日、吉祥寺「曼荼羅」での月例「短歌絶叫コンサート」も38年を迎えた。
☆本記事は皓星社メールマガジンにて配信されました。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。