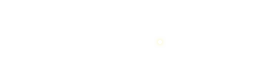福島泰樹(歌人)
昭和21年1月、13歳の長澤延子は、詩「白雲」を書き、2月11日、14歳の誕生日を迎えた。3月に、5行3連からにる「うた」を書き、「友よ冬のうれいを捨て去れ/新しい喜びに声高く歌おう/春のうたを」と友に呼びかけ、7月には、短詩「わかれ」をしるしている。
「あなたは冬のような人ね」と
つぶやいた あの人……
いまも私の胸に残っているさゝやき
あなたは夏の人……私は冬の人
あまりかなしい二人が
はなればなれになったとて
何の不思議があるだろう
あなたは夏の空に
あなたの歌をうたうし
私は冬の空に
私の歌をうたう
「白雲」「うた」「わかれ」ともに友との別れがテーマになっている。
この「友」とは誰のことだろう。そして8月「おぼろな物語ヨリ」と副題のついた創作詩「幻の十二階」を書く。延子は、焼け死んでゆく青年に問う。「お前は何故死んだのだ/この塔を守るためにか?」。若者は応える。「俺達が悪いんじゃない/呪われた塔よ!」と。青年を燃やし、燃え尽きて倒れてもなお、「……宙に浮く/幻の十二階」。延子は「幻の十二階」に何を幻視したのか。
敗戦の日から1年を迎えた8月にこの詩が書かれている。ならば、戦い敗れても、いまだ宙に浮く十二階を、「国体」日本と捉え、若者を戦死した兵士と解するのは安直すぎるだろうか。
昭和20年8月15日、桐生高等女学校2年生の延子は、勤労動員先の工場で敗戦を聞いた。8月末から徐々に授業は再開されていった。空襲をまぬがれた桐生の街にも、闇市の露店がならび、進駐軍の兵隊が市内を闊歩した。この時代の雰囲気を日沼倫太郎は長澤延子論で、「熱に浮かされたような精神の狂熱と、死灰を食む、さむざむとした絶望とが入りまじ」り、「久方ぶりに訪れた平和に私たちは狂喜した」「奇妙な解放感と希望とが共存していた」(『自殺者の系譜』)と、伝えている。
しかし、延子のこころを占めたのは「熱に浮かされたような精神の狂熱」でも「奇妙な解放感」でもなかった。
敗戦の半年余りが過ぎて書かれた短歌作品30首余りが遺されている。その多くは、「胸病める君眼差しのひえびえと川波ゆるる我が胸にあり」「すべてみないつわりに見ゆる心かなしうつうつと空ににじみ出るひとみ」などにみられるように、仮想の友への儚い恋慕と、虚偽に満ちた世界を見ることの悲しみである。延子の詩には、明治以来、少女たちが書き綴ってきた抒情詩が醸す気分や情緒の類は一切ない。その底流を厳かに流れるのは、思想であり、虚無であり、ニヒリズムであるのだ。
「幻の十二階」に続く4作目の詩「折鶴」を引く。11月になって書かれている。
紫の折鶴は
私の指の間から生れた
ボンヤリと曇った秋を背中にうけて
暗い淋しい心が折鶴をつくる
あゝ 秋は深く冬は近い
机の上にひろげられた眞白なページに
今日もインキの靑さがめぐっている
友よ 何故死んだのだ
紫の折鶴は私の指の間から生れた
落葉に埋れた あなたの墓に
私は二ツの折鶴を捧げよう
私とあなたは 折鶴など縁遠い存在だったけれど
あなたが私の許を去った日から
何故か折鶴が あなたの姿のように見えるのだ
もの言わぬ あなたの墓に
私は二ツの折鶴を捧げようーー紫の折鶴を
あなたと私とのはかない友情を表した
あの淋しい折鶴を
中原中也や立原道造が得意とした4、4、3、3の4連14行からなるソネット形式とは違った、4、3、4、3、4行の5連18行からなる形式を14歳の詩人は、どのような経緯を経て創造したのであろうか。彼女に影響を与えた詩人がはたしていたのであろうか。いたなら誰であったのだ。鮮やかな出来映えの詩を前に、さまざまな思念が湧きあがってくる。
まこと「折鶴」は、詩人長澤延子の誕生を飾る詩である。この詩に至るまでおそらく、相当の修練を経ているはずだ。しかし、残されたのはわずかに5編。ノートに書き写されることなく波間に沈んでいった詩や言葉の断片を思う。
そして、繰り返し歌われることとなる。「友」とはいったい誰のことなのだろう。最初の詩「白雲」(13歳)がノートに標されたのは、昭和21年1月。この詩では、友との死別を予感させはするが、直接的に死は語られてはいない。3作目「わかれ」には死の影はない。そして5作目「折鶴」に至り友との死別が歌われることとなる。
「紫の折鶴は/私の指の間から生れた」。第1連で、情景が鮮やかに歌いこまれている。2連では季節の移ろいをしるし、3連目で友の墓へと場面を移動、二つの折鶴を献じた理由を4連目で問い、終章に至り紫の折鶴が「はかない友情」の標しであると、7音、5音を基本としたゆったりとした拍子で歌われてゆく。
ところで、この詩で歌われている「友」とは、誰であろうかと、再び問う。
そうだ、『長澤延子全詩集』解説で私は、このように記したのだ。
「友よ」の「友」は、自身への呼びかけではないのか。墓にいる自身に、向かって「紫の折鶴」を折るという、生と死の「複合」によって成り立った詩ではないのか。長澤延子は、十四歳十ヶ月にして、一気にその自身の詩の方法を獲得してしまった。「生」の此岸から、「死」の彼岸に呼びかけ、「死」の彼岸から「生」の此岸を照射するという方法、いや生の在り方をである。
「生と死の複合」とは、生者である私と、死者となった私が、呼び呼ばれて一体となって織り成す世界の謂いである。「二ツの折鶴」は、その象徴として折られたのである。そして、「折鶴」の詩は、同じくこの11月の、4連11行の短詩「寂寥」へと連なってゆくのである。これも、声にだして読みたくなるような詩だ。
限りないさびしさに
全身があおざめる時も
私はたった一人ぼっちなのだ
冬は来る!
冬の寂寥に魂を投げこもう
私のさびしさをまぎらすために
生きることは さびしいのだ
…雪に埋れた私の上を
春の風が吹く時…
友よ 私はほゝえんで
ながい旅に のぼろう
「寂寥」は、後に書かれることとなる「友よ/私が死んだからとて墓參りなんかに来ないでくれ」に始まる長詩「別離」の下書きとさえ思われてならない。冬に向かって延子はこの月、「折鶴」「寂寥」「冬」「若さ」という4作品をなした。
福島泰樹(ふくしま・やすき)
1943年3月、東京下谷生。早大卒、69年、歌集『バリケード・一九六六年二月』でデビュー。「短歌絶叫コンサート」を創出、朗読ブームの火付け役を果たす。85年4月、「死者との共闘」を求めて東京吉祥寺「曼荼羅」で「月例」コンサートを開始。ブルガリアを皮切りに世界の各地で公演。国内外1700ステージをこなす。単行歌集に『下谷風煙録』(皓星社)他33冊、全歌集に『福島泰樹全歌集』(河出書房新社)。評論集に『弔いーー死に臨むこころ』(ちくま新書)『寺山修司/死と生の履歴書』(彩流社)、『誰も語らなかった中原中也』(PHP新書)、『追憶の風景』(晶文社)。他にDVD『福島泰樹短歌絶叫コンサート総集編/遙かなる友へ』(クエスト)など著作多数。毎月10日、吉祥寺「曼荼羅」での月例「短歌絶叫コンサート」も37年を迎えた。
☆本記事は皓星社メールマガジンにて配信されました。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。