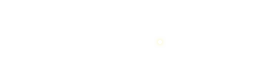今年2022年は、詩人・長澤延子の生誕90周年という節目の年です。長澤延子は群馬の桐生市に生まれ、戦後まもなく17歳という若さで夭折。しかし、彼女の清冽な詩は、死後友人らによって刊行された遺稿詩集『海』によって広まり、60年代という叛乱の時代を生きる若者たちの胸に深く刺さりました。
本連載【長澤延子生誕90周年 母よ、黒い旗で遺骸を包み……】では、昨年刊行の『長澤延子全詩集』の編者・福島泰樹さんに、1月のご寄稿「友よ、私が死んだからとて」を導入として、長澤延子という詩人の魅力、そして作品に宿る力強さについてご執筆いただきます。連載は隔月奇数月を予定しております。(編集部)
1949、昭和24年5月末、17歳の命を断った長沢延子。彼女の詩集『海』、正確には『海 長澤延子遺稿集』が、実父長澤竹次の申し出を受けた新井淳一、高村瑛子ら友人の手によって編集、刊行されたのは、延子没後16年の1965年10月であった。ほどなく延子の詩は、1960年代後半の政治的嵐が吹き荒れる激動の時代に、闘う学生たちによって迎えられた。都市出版を立ち上げた矢牧一宏篇による『友よ 私が死んだからとて』の延子の詩と手記に、学生たちは自身の言葉を体現した。
たとえば、死の年の1月に書かれた「墓標」と題する詩の一節……。
雪よ あの家を埋めろ
私の墓標はこの涯ない草原に群をなす
裸体の人々の中にある
すでに家を捨てた者が
逞ましくこの草原を闘いの色に染めあげている
私は一本のわかい葦だ
傷つくかわりに闘いを知ったのだ
打ちのめされるかわりに打ちのめすことを知ったのだ
雪よ 闘いの最中にこの身に吹きつけようとも
もうすでにおそい
私は限りない闘いの中に
私の墓標をみた 「墓標」
「墓標」を書き写しながら私は、1969年1月、攻防戦陥落後の東大安田講堂の壁に書き記された「君もまた覚えておけ/藁のようにではなく/ふるえながら死ぬのだ/一月はこんなにも寒いが/唯一の無関心で通過を企てるものを/俺が許しておくものか」、あるいは「連帯を求めて孤立を怖れず/力及ばずして倒れることを辞さないが/力を尽くさずして挫けることを拒否する」などの檄詩を思い起こしていた。
以下、長沢延子詩の来歴と、その人の生立ちを少しく書き散らかし、本論に入ることにしよう。
1
1949年3月、自殺を決行するにあたり、長澤延子は、大学ノート2冊に1946年1月(13歳)から、49年3月(17歳)に到る5年2ヶ月の詩85篇(+短歌36首)を書き纏めた。
自殺決行の3月26日夜、196行からなる長編詩を、意識が朦朧とする瞬間まで書き続ける。……が、自殺に失敗。
数日後、大学ノートに「手記」を書き始めると同時に、詩を書き始める。
5月31日、「ほがらかな五月の青空を/何時ものようにみつめてさよならです」の遺書を書き残し死去。この2ヶ月余りに実に40篇もの詩を大学ノートに書き記し、大学ノート2冊にびっしりと「手記」を書き遺した。
『長澤延子全詩集』(皓星社)を編纂するにあたり、私は、残された3冊の大学ノートを「詩集ノート[A]」「詩集ノート[B]」「詩集ノート[Note Book]」の3冊に分類した。「詩集ノート[A]」には、「1946年1月」から「1948年」「11月」までの詩を、「詩集ノート[B]」には、それ以後の11月から、「1949年」「3月」までの詩を収録した。「A」「B」の分類は、延子自身によって大学ノートに大きく記されたものである。
「詩集ノート[Note Book」には、1949年3月26日自殺失敗以後、5月31日服毒に到る詩篇が書きしるされているが、ノートに標題はない。したがって「詩集ノート[Note book]」と名付けた。手記を収めた2冊の大学ノートには、それぞれ大きな字体で「手記A」「手記B」の記述が在る。
2
長澤延子、1932(昭和7)年2月11日、群馬県桐生市小曽根町に長澤竹次・タツの次女として生まれる。姉キヌは6歳で、兄弘夫は3歳であった。——だが、この時代は、年号の方が述べやすいので、しばらく年号で書き進めてゆく。
桐生は、奈良時代にさかのぼる絹織物の名産地で、ノコギリ屋根の工場と古い商家が甍を連ね、日本を代表する機業都市である。2・26事件のあった昭和11年3月、4歳になったばかりの延子は、生母タツを喪う。棺に納まった母の死に顔と焼場の玉砂利にひとり遊ぶ情景が、詩人の最初の記憶であった。
翌12年春、幼稚園に入園。5月父、中島かつと婚姻届提出。生母タツが病死してから、まだ1年が過ぎたばかりではないか。幼い魂が震えないわけはない。6月には、弟恒夫が出生している。7月、盧溝橋事件が勃発。以後、延子は戦争の時代を生きることとなるのだ。
義母かつは、桐生の人。結婚にあたり先妻の写真の全てを焼却することを求めた。そのため延子は、鮮明な母の面影をたどることができなかった。
だが教養人の継母は、文学書や教育書に加え、当時は稀少な蓄音機、世界名曲アルバムなどの文化を家にもたらしてくれた。
ところで6歳年長の姉は、延子が小学校に入る頃には、家を離れ前橋の共愛学園女学校に入学し寄宿舎生活を始め、卒業後は東京新宿の文化服装学院に進み寮生活を続けた。姉が桐生の家に留まっていれば延子もまた、違う歩みをしていたことであろう。とまれ、昭和13年4月、桐生市立西尋常小学校に入学した延子は、兄や家の蔵書を読破してゆく。
翌14年春、38歳の父に召集令状が舞い込む。しかし、中国出征の直前、発病。自宅待機を命ぜられる。戦争の進行と共に、成長してゆく少女、そしてその魂の来歴を延子は後に、こう綴った。
事実を語ろう。
——私の幼年時代は
心に虚無が吹き荒れていた。
本当に幼ない ちいちゃな頃から。(略)
私の幼年時代はただ暗い寒い——それのみだった。
表面は暖かい両親に抱かれてそれこそ我がまま一ぱいに育って来たが。 「手記B」
昭和19年4月、群馬県立桐生高等女学校入学。延子は12歳になっていた。延子は突如、今泉町の伯父長澤利脇の家に移り住むこととなるのだ。
伯父が経営する織物工場(長利織物)は、最盛期には市内1200軒を越す工場に中にあって屈指の機業を誇っていた。しかし戦況は厳しさをまし鉄製力織機は供出のやむなきにいたり、織物の生産は休業に追い込まれていた。事情は、延子の生家も同じことで、父は市内に設立された航空機部品製造会社の役員として、毎朝自転車で通勤していた。
伯父には子供がなかった。だからといって養女に出すほど父の家は逼迫してはいなかった。人一倍に家族を愛し、子煩悩な父であった。しかも伯父と父とは、血でつながってはいなかった。ならばどのような事情で、一人娘を血縁者でもない人のもとへ遣らなければならなかったのだろうか。延子と継母との不仲が原因であろうか。いや、そうではあるまい。おそらく、伯父と父と間には、そうせざるをえなかった理由が、存在していたのであろう。
このことは、群馬県内の中島飛行機(太田市)で就労中の兄にも、東京で就労中の姉にも何一つ知らされることはなく、血を分けた姉兄にも見送られることなく、延子は伯父の家へ貰われて行ったのである。そして、伯父夫婦の目論見は、成績優秀な延子を養女とし、やがては優秀な婿をもらい受け、長利織物を継がせることにあった。しかし、延子の手記には、この間の経緯は一切書かれてはいない。
やがて自身の境涯などよりもさらに大きな関心が、延子のうちにもちあがってくるのである。
3
延子は、営業を停止した母屋に迎えられ、12歳の少女に個室が与えられた。孤独を得た延子は、以前にも増して読書に熱中、この頃から詩を書き始めた。しかし、その詩は遺されてはいない。わずかに、「その頃は、藤村、春夫、ヘッセなどに惹かれスタイルも真似ていた」(『海』あとがき)という高村瑛子の証言があるのみである。また、延子自身によっては、「一年生の時愛誦した詩/アイヒエンドルフ「元気な出発」」という記述が「手記A」にある。ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフは、19世紀のドイツのローマン派の詩人。延子は、次なる詩句を引いている。
〝出かけよう——
此の旅が、何処で果てるかは僕は問はない。〟
〝輝きに目もくらみ、浄福にひたされて!〟
〝大きな河を〟〝渡らう〟 「手記A」
この年、学徒動員が始まり、12歳の延子も、陸軍被服工場となった女学校で、セーラー服にもんぺを着、日の丸の鉢巻き姿で兵士のワイシャツや下着を縫い続けた。クリハラ冉篇「長沢延子略年譜」(「江古田文学」68 長沢延子特集号)によれば、「夏頃、母かつの実家である広沢町に母、祖母、姉、弟らと疎開」とある。六歳上の姉と親密な言葉を交わしたことであろう。
昭和20年になると空襲警報が頻繁に発令。8月15日、13歳の延子は勤労動員先の工場で敗戦を聞く。クリハラ冉の年譜が晴れやかに歌いだす。「8月末より徐々に授業再開。疎開していた女学校の蔵書も少しずつ戻ってくる。この頃から映画、スカート等解禁。」「桐生市内には露店が並び闇市で賑わう。米兵、桐生に進駐。」
それにしてもと思う。群馬県下の都市で、桐生市だけが空襲を免れたのはなぜだろう。アメリカの占領政策の中に、桐生は組み込まれていたのであろうか。それとも、絹織物に対する彼らの信仰がそうさせたのであろうか。長澤延子の詩と思想を考える時、このことは実に大きな意味あいをもってくる。
焦土と化していたら、長澤延子の詩の土壌も失われていたことであろう。
4
大学ノート「A」に書かれた最初の詩は、短歌だ。
表表紙を開くと最初の頁に、『「15才の詩集」ヨリ』とあり、×印のあと、短歌2首が標されている。
芽生えたる柳の緑色浅く春来てかすむ街の並木路
夕映えに我が身かざりて散る櫻諸手にうけて君に捧げむ 「「15才の詩集」ヨリ」
さて「15才の詩集」より、ということであるが、「15才」は数え表記で満年齢では「14才」ということになる。2首の後に続く詩「白雲 ——甘利さんに——」には、「1946.1月」と横書きで、制作年月が標されている。延子の生年月は、1932年2月であるから、この2首とこれに続く詩作品は、13歳の作ということになる。短歌2首であるが、ノート巻頭に置いたからには、思い出ふかい作であったのだろう。敗戦、そして初めて迎えた春、忙しげな息遣いの中に青春の、早急な萌芽を感じさせる。
さて、2首目、両手を重ねて受ける桜の花びら、この君とは誰のことか。
2首の後を「白雲 ——甘利さんに——」と題する短い詩が続く。君とは、甘利さんのことであるのかもしれない。
ほのかなる白き雲ゆるやかに空を流る
愛する友よ あなたはあのように美しく そしてやさしい
あなたとお別れした時にも 眞靑な夏の空に
美しい白雲が浮んでいた エンゼルのように——
友よ あの白雲は私たちを結ぶ友情のシンボル
私は白雲を見る度にあなたを思う
あなたも私達のことを思って下さるだろう
友よ あの白雲が大空に漂よう限り
私達の友情は永遠にほろびない 「白雲 ——甘利さんに——」
ところで、標題の「甘利さん」とは実在する人物であるのだろうか。そうではあるまい、7行目には、「あなたも私達のことを思って下さるだろう」とある。「白雲」となって地上の「私達」を眺めているという構図だ。
この「友よ」への呼びかけ、13歳最後の冬の日に発せられた「友」へのあふれるばかりの欣求のこころ……、以後延子の詩は、その死まで3年と6ヶ月。この友への呼びかけが主調音となって、ちから勁く書き進められてゆくのである。
長澤延子(ながさわ・のぶこ)
1932年、絹織物と養蚕の町、群馬県桐生に生まれる。4歳で母と死別、読書と思索の日々の中で死への欲求は少しずつ育つ。1949年高等女学校卒業後、詩と手記を清書した5冊のノートを 親友・高橋瑛子に托す。同年6月1日、服毒。17歳だった。
『長澤延子遺稿集 海』(1965年、私家版)、『友よ 私が死んだからとて』(1968年、天声出版)など、これまでに多くのアンソロジーが組まれ、その度に大きな反響を呼んできた。
福島泰樹(ふくしま・やすき)
1943年3月、東京下谷生。早大卒、69年、歌集『バリケード・一九六六年二月』でデビュー。「短歌絶叫コンサート」を創出、朗読ブームの火付け役を果たす。85年4月、「死者との共闘」を求めて東京吉祥寺「曼荼羅」で「月例」コンサートを開始。
同年6月、短歌絶叫コンサート「六月の雨/樺美智子、岸上大作よ!」を開催。ブルガリアを皮切りに世界の各地で公演。国内外1700ステージをこなす。単行歌集に『下谷風煙録』(皓星社)他33冊、全歌集に『福島泰樹全歌集』(河出書房新社)。評論集に『弔いーー死に臨むこころ』(筑摩書房)『寺山修司/死と生の履歴書』(彩流社)、『誰も語らなかった中原中也』(PHP新書)、『追憶の風景』(晶文社)。他にDVD『福島泰樹短歌絶叫コンサート総集編/遙かなる友へ』(クエスト)など著作多数。毎月10日、吉祥寺「曼荼羅」での月例「短歌絶叫コンサート」も37年を迎えた。
☆本記事は皓星社メールマガジンにて配信されました。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。