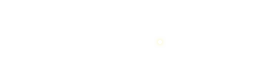神保町のんしゃら日記18(2025年6月)
1日(日)新しく依頼をする著者との約束に間に合わなくてすっぽかしてしまったあと、道に迷って(しかも自宅最寄り駅の目の前で)、正しい道に戻れない、という夢……。こういう夢を見ている時、意地でも「正しい道」「正しい対応」に戻りたくて、解決するまで寝ていようとしてしまい、遅寝になったり遅刻しそうになる。他にも、乗り換え検索アプリで正しい経路を検索できない(で終電に乗れない)とか、靴紐がいつまでも結べなくて家から出られない、というのもあったなあ。結局起きても、気分の悪さが残る。
午後、気持ちを切り替えて技術書典に行ってみる。技術の本の文フリで、大賑わい。ほとんどの本は私には理解不能なんだけど、興味深い。これらの展示会にきて冊子を買っている人たちは、同じ日本語を話しているとしても外国語を話しているようなもの、ということなんだろう。最近技術者の方とのコミュニケーションで悩むことが多いのだけど、違う言語を使う者同士なら、意思疎通が難しいのは当然のことだろう。面白かったのは、紙版を買うと電子版(PDF版)も同時にダウンロードできるということだ。これは商業出版者にはない思想だろう。販売しているものが「情報」ならば、買った情報を「どの形態で」読むか読者が自由に決められるというのは、いい仕組み(ただし逆=電子を買ったら紙をもらえる、は成り立たない)。既存の仕組みでなにかできないかなあ、など考えるともなく考える。ちなみに、「技術書典アプリ」なるものがあらかじめ用意されていて、決済もアプリでできた。財布を一度も出さずに本を買い回れて大変快適。さすが技術者集団のブックイベントといったところ。
帰ってきてから、昨日収穫した4キロのそら豆の一部で、豆板醬を仕込む。茹でて潰して、塩麹と唐辛子をまぜ、あとは半年後まで発酵させる。さて、うまくいくかどうか(8月現在順調)。
2日(月)『写真師 島隆:明治・幕末を駆け抜けた日本女性初のフォトグラファー』(後日、副題を「日本初の女性フォトグラファー」に変更)。ゲラを著者の蓑﨑昭子さんに送る。校了まで、あと少し!。昨日6月1日は長澤延子の命日だった。
蓑﨑さんとの縁は『長澤延子全詩集』を桐生タイムスで紹介してくれたところから始まった。今回、桐生の人の本としては2冊目となるこの本を出すことができてほんとうに嬉しい。夫の島霞谷と一緒に英語や写真術を学んで吸収していく過程もいいが、霞谷の没後、桐生に帰郷してからの写真館設立、マンガン鉱を売り出したり、養子も何度もとったり、とにかくいろいろなことをやった。でも女性の歴史はなかなか残らないから、追いかけ、記述するのも難しい。記録の断片から全体像を浮かび上がらせようとする、蓑崎さんの見事な手腕による一冊を読者に届けたい。営業営業!
4日(水)今日から石川県出張。行きの電車の中で新聞を読む。今日から夫婦別姓法案の質疑がはじまり、実質審議入りとか。結婚して夫婦が(というか事実上ほぼ女性側が)別の姓を選べるようになったとして何も困ることはない。早く進めー! いっぽうで、婚姻なんてしなくてもとくに問題はない、というのがこの10年の実感でもある。住民票を一緒にしていれば日常生活で困ることはないし、まだやっていないけど、相続についても遺言や法定調書を残しておけばいい。お互いの家族と良い関係でいることと、法律婚の有無とは無関係だ。だとしたら、このような信頼のおき難い国家に個人の大切な人間関係を承認してもらうことに、どんな意味があるだろうか。もし法律ができたとしても、今のところ私たちは婚姻しないつもりだ。でもそれとは別に、別姓法案は通ってほしいし、そうなれば(少しは)この国家を見直すというものだ。営業終了後、金沢在住の著者と会合。
5日(木)今日も北陸の営業。うまくいくことばかりではないが、ひよどり亭、というお店で食べたお昼のとんかつがとっても美味しくて気を取り直す。丸善雄松堂さんの営業の方のおすすめとか。地元の営業の方のおすすめはまず間違いない。神保町でガッツリ昼ごはんを食べることはあまりないけど、こういう時は別で、モヤモヤを食欲に変えて思いっきり食べる。野生味のある肉肉しいトンカツだった。夜はいつもなら飲みに出るところ、倒れ込むように寝てしまった。
6日(金)営業が福井県で終わったのでそのまま敦賀の「ちえなみき」に足を延ばしてみる。運営はは丸善雄松堂。編集工学研究所の選書となる、図書館でも書店でもない、新しい形の本とのタッチポイント、ということのようだ。ここにある本は買ってもいいし、ワーキングスペースで読んでもいいそうだ。市の施設なので、本は出版社からの委託品ではなく買切品という点が、図書館でも書店でもない場所、という所以だ。人と本の関係はこれからどうなっていくか、その模索の過程を見た気がする。
7日(土)敦賀からの帰り、横浜で降りて、昭和ポップス愛好家のさにーさんのイベントを見て帰る。(現在、楽しい本を計画中)。
8日(日)久しぶりに家にいる朝。庭に水をやる。やばい!!ブルーベリーの実をすずめが物色している……!来週には防鳥ネットせねば!!!
午後、綿田友恵さんの黒田和美賞(月光の会で出している年間の賞です)授賞式。綿田さんおめでとう!大好きな月光会員の皆と短歌や文学について延々呑みながらしゃべる。
9日(月)『鎌田セレクション6鉄鋼産業の闇』月報の校正依頼を送るなど。出張から帰ってきた直後なのでばたばた。
10日(火)蓑崎さんに『写真師 島隆』カバーラフと口絵の案を送る。日本女性初の写真家のノンフィクション、ということで歴史物だけど、当時としてはすごく新しいことをやった人なので、その新しさがでるように、写真は隆の(つまり幕末の)を使いつつ、ポップな感じの装丁に……といういつもながら無茶なお願いを亮一さんにしたのだけど、いい感じになった。気に入ってもらえるといいのだが。 晩御飯は久しぶりに家で二人で食べる。同じタイミングで出張していたIさんのお土産のくさいモツ煮(大正屋)をおなかいっぱい食べる。このばあいの「くさい」はもちろん褒め言葉。
11日(水)朝の電車内、向かいに座っている人が編み物をしている。華奢な指先から深い青色の毛糸が川のように編み出されていく。綺麗だなあ。食べものも、着るものも、手づから生み出せないものは何もないはずなのに、一体私は何にあくせくしているのか……などと思ってしまう。新聞一面は東海村村長が、東海第二原発の再開容認のニュース。村長64歳。退職金をもらうまで逃げ切れればあとは関係ないのだろうか。今日は関東県内を営業。
14日(日)十余年使った電子レンジが壊れたので新調。痛い出費だが毎日使うものだし、食事は生活の基本なので、いろいろ調べてPanasonicのBISTROの中位機種を買う。なんと、ゆで卵や温泉卵がレンジで作れるらしい。画期的。
17日(火)今日から京都・大阪営業。朝イチから回るので本当は前入りしていると楽なのだが、昨日は夜約束があったし宿泊費もかかるので、出張は早出・最終便が基本だ。頑張って切り詰める。ホテルもどこも高いのだが、ここ2回ほど京都出張時には「京都ユニバーサルホテル烏丸」に泊まっている。京都駅まで徒歩圏内で部屋もほどほどの広さ。すごいのは、朝だけでなく夕食もついてきて、平日なら5000円ほどということ。
19日(木)同行営業2日目。今日と明日で奈良と大阪をまわる。今日は担当さんのおすすめのラーメン「熊きち」で塩とんこつラーメン。美味。今回は大阪万博もあって大阪のホテルが高いので、夜は奈良に移動して、明日朝からの営業に備える。奈良と大阪、意外と近い。
20日(金)奈良の後、再び大阪へ。営業の最後にMoMoBooksさんに寄る。パレスチナの本のフェアをするというので、早尾貴紀先生の『パレスチナ、イスラエル、そして日本の私たち』を仕入れてくださったお店。最寄駅の九条駅から10分弱歩いた、長屋ふうの路地の間にあった。展示「セックスワーク イズ ワークやっちゅーねん~「冊子STOP!買春処罰法:セックスワーカーの安全と健康のために」」をみて、店のお二人とお話しし、SWAHS編『セックスワーク・スタディーズ』(日本評論社)と、お店の開店から1年までを描いた『MoMoBoo絵日記』を買って帰る。
お店をでると、どこからともなく優しそうなお婆さんが現れ「どこから来たん〜」「駅はあっちやで!」「帰る前にお母さんに電話してあげてな、よろこぶで〜」と声をかけてくれ、駅までの道をくわしく教え、見送ってくれた。なんか絵に描いたような地元のおばあちゃんだなぁ……と思いつつ電車の中で『絵日記』をひらくと、明らかにさっきのおばあちゃん(作中ではばぁば)が随所に登場するではないか!もう、絵に描かれてました。(この絵日記傑作でした。訪問の方はぜひ購入を!9月5日にこちらで早尾先生の講演もあるとのこと)
22日(日)クエを食べる。高級魚のクエである。もちろん、私にそんな財力はない。相方のIさんが船釣りで釣ってきたもの。魚はよくご相伴に預かっているが、ここまでのものは滅多に無い。友人Sさんがきて捌くのを手伝ってくれ、久しぶりに界隈の皆で一緒ににぎやかな晩御飯になる。
23日(月)『調べる技術』10刷(2022年刊)、『書庫をあるく』2刷(2024年刊行)の発注。「増刷をかけたら実売が止まった!」はよくある話だが、この2冊は堅調に売れてそれぞれここまで来てくれている。どちらも著者の地道な発信のおかげ。感謝。
27日(金)こうでなければなならい、当然こうだ、という道、思考からできるだけ自由になりたい。舗装された道、というわけではなくても、自分が「道」だと思ったところを私はすすんでいる。何もない草むらを歩く時でさえ、自分の認知の道から外れて自由にあるくことは難しい。読書猿さんの新著『ゼロからの読書教室』(NHK出版)を読んで思うこと。
(後日、この本と小林昌樹さんの『立ち読みの歴史』の刊行記念で対談をしました!→特別対談 読書猿×小林昌樹新著刊行記念 なぜいま、“読書”に注目が集まるのか?)
日中、Iさんがブルーベリーに防鳥ネットを張ってくれたので、これでブルーベリーの鳥害問題は解決。
28日(土)朝刊、座間の9人殺害事件の犯人に死刑執行のニュース。ゆううつ。死刑は国家による合法的な殺人なのだ。そんな制度が容認されている社会であることに何度でも落胆する。
庭では、今年はじめて挑戦しているスイカの実が大きくなってきた。
30日(月)嫌な夢を見て寝覚めが悪い。でも早めにおきられたので、きゅうりとラズベリーを収穫して気分を上げてから出勤。 神保町のタウン誌『新・本の街』に寄稿する原稿を書いていて、郷土愛、地元愛、ということについて考える。一時期をすごしたことに由来する親しみはあるけど、それは「愛」と呼ぶようなものではない気がする。むしろ複雑なもの、自己嫌悪感や罪悪感と、地元というものに対する思いというのは結びつきが強いようだ。自分で選ぶことができなかった、好むと好まざるとに関わらず私に一部になった場所であり、捨ててきたというほどではないが、そこに居続けることを選ばなかった場所でもある。多くの地方出身者は、出身地に対して、はたしてどういう思いを持っているものなのだろうか。