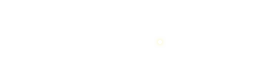神保町のんしゃら日記13(2025年1月)
1日(水)死者の顔というものは、このように日毎おだやかに、うつくしくなってゆくものであろうか。午前中、大叔父に線香をあげ、蒼前神社で元朝まいり。夜にはまた大叔父の家に線香番をしにいく。亡くなった大叔父の妻のKおば(私の祖父の妹)、その妹のSおばらと一緒に晩ごはんをたべる。昔の話をいろいろしてくれる。祖父が営んでいた魚屋(卸売と店売り両方やっていて、看板はなかった)の話。家の前の「がんじゃ川」(米を研いだり、日常生活に使う水が流れていた水路のことらしい)で「ホヤ」を洗って食べたこと。二人の叔母は九人兄弟の末子なので、私の父とも年が近く、一緒に暮らしていた時期もあること(だからおば・おいというより姉弟のような関係)。その頃の家の作りや、私たちのひいひいおじいさんの話など。きれいな顔でねむる人を横に、えんえんとそんな話をきいた。親の昔の話も、改めてこういう機会がなければなかなか聞けるものではない。そのまま泊まって線香の番。
2日(木)朝、葬儀会社の人がきて、死装束を着せ、お金を持たせる儀式。葬儀会社は生協系列の会社。担当はずいぶん若い人だが、たたみのへりを踏まなかったり、座布団は横に置いて自分は座らなかったりと、顧客の家における礼節の要所をよく押さえているものだと感心した。
4日(土)昨日の夜から急に発熱。午前中病院へ行き、インフルエンザでもコロナでもないことはわかり一安心。午後には熱も下がる。知恵熱?
5日(日)火葬とお葬式。葬祭センターで焼香し最後のお別れをしたあと火葬場へ。2時間ほどで焼き終わる。物体としての人間の体はこのように、すぐ抱えられる大きさの箱に収まるだけの骨になってしまうものなのか。おじちゃん、可愛がってくれてありがとうねと思いながら、せっせと骨を拾った。お葬式でと初七日の法要を一緒にすませ、また大叔父の家に戻り、なおらい。お酒を飲みながらまた昔話をいろいろ聞く。
田舎だからということもあるだろうけれど、なおらいで立ち働くのは女ばかりだ。せめてここにきていた子供たちにこの光景が染み付いて再生産されないようにと願わずにはいられない。夜、盛岡駅前から妹と夜行バスに乗る。熱は下がったが今度は咳が出てくる。
6日(月)今日から始業なのに、夜行バス明けのうえに咳が抜けない。新年からボロボロ。水谷さんからお菓子がいっぱい詰まったタッパー(去年、忘年会のために仕込んでおいた煮卵を、忘年会がナシになったので容れ物ごとあげた)が返ってきて癒される。今年も頑張ります。早く治さないと。
7日(火)4月に刊行する早尾貴紀さんの単著のタイトル(担当楠本)は『パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたち 〈民族浄化〉の原因はどこにあるのか』に決まる。編集だけでなく営業ふくめて時間をかけて考え、著者と議論を重ねて決めた。2023年10月以降パレスチナ関係の本は色々でているけれど、この民族浄化は、日本で生活している自分とどう関係があるのかを書いた本という点で類がない。読めば、遠い中東のことではなく「自分ごと」として捉えられるようになる、そんな内容になっている。
9日(木)東京堂で『新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史』(フリート横田著、毎日新聞出版)を買う。年末年始に祖父(テキ屋)の話を聞いたばかりなので、久しぶりにテキ屋関係のことを知りたい気持ちが再燃してきたところに、ちょうどいい新刊がでていた。夕方、母と妹からインフル罹患の連絡。私もまだ咳がぬけないが、もう熱もないし……と呑気にしていたら「周りの人のことも考えてもう一度病院にいきなさい」と楠本さんに叱られる。すいません、おっしゃる通りです。
10日(金)念の為もう一度病院に行くが何も出ず、一安心。午後遅めに2時間ほど昼寝するとすっかり快復していた。ピークを超えたからこれでもう大丈夫、と体感でわかる。夕食をもりもり食べる。体調不良でも食欲が衰えない方なので、ピークを超えれば回復は早い。
13日(月)祝日。年末に妹にすすめられたnotionの動画をみてみる。うまく使えば仕事の共有、管理など合理化できるかも。合間を縫って勉強してみよう。
14日(火)今年最初の企画会議。いくつか新しい企画が決まったり、棄却したりされたり、
17日(金)鎌田慧セレクションが「東奥日報」で取り上げられ、掲載紙が届く。取り上げてくれたのは、斎藤光政記者。斎藤記者は鎌田さんと『下北核半島』の共著などがある。鎌田セレクションは3巻を今日入稿。年末年始の不幸や風邪もあって最後の確認に時間がかかってしまい、今回も亮一さんに苦労をかけた。
19日(日)読売新聞に南陀楼さんの『書庫をあるく』の書評が掲載される。評は清水唯一朗さん。「 図書館は雪のようだと思う」という静かで美しい書き出しに周りの生活音が消えるような感じを覚える。県立長野図書館の写真を使い、ご自分と著者を「同志」と書いてくれたことも嬉しい。来週から、笹森さんには早速これをもってフォローをしてもらう。店頭での実売の追い風になってほしい。
23日(木)今年出す(予定)の本の打ち合わせ2件。
24日(金)会計関係の打ち合わせのあと、午後は河原さんと打ち合わせに出かける。去年ベータ版をリリースした「じんぶつプラス」との連携を模索中のデータベースを運営している方々と。前向きに進みそう。
26日(日)午前中はnotionの勉強。ちょっとしたことがうまくいかないとすぐ詰まるけど、面白い。最初はデジタルツールの使い方ならYouTube?と思って勉強を始めたけど、いまいちよくわからず、入門書何冊かにざっと目をとおしてようやく、できること/できないことの全体像がわかってきた。一方、細かい作業や動作については本ではよくわからなくて、個別具体的な挙動で迷ったときは、本と動画を併用してみている。技術の進歩に伴ったツールのアップデートのスピーとは早い。紙とデジタルをうまく往還するのが効率良く学ぶコツと言えそうだ。 午後、月光歌会。《ここにいてここにはいないその人は夢みるように目を瞑りつつ》を出す。年末の別離の所感を詠んだもの。重信房子さんが新著『ただいまリハビリ中 ガザ虐殺を怒る日々』(2024、創出版)を持参されていたので購入し署名をもらう。帰りの電車で、半分はこの本を、半分はもうすぐ返却期限の『朝鮮大学物語』(ヤン・ヨンヒ著、2018、KADOKAWA)を読む。家に帰るとIさんがケーキを買っていてくれた。ありがとう。誕生日でした。
27日(月)水谷さん、河原さん、笹森さん、私の4人で昼ごはんに行く(他の人は休みや外出)。水道橋近くの「龍樹房」は皓星社の社食・たいよう軒なきあと、よく使われているようだ。たしかに800円前後で量もじゅうぶんあり、メニューも多いし、中華料理なのでボリュームもあってコスパがよく、食後の杏仁豆腐もクオリティ高し。社員さんと飲食しない経営者も多いというけど、私はこういう時間を大事にしたい。話しながら食べていると、皆それぞれに言葉にしない部分のこだわりや考え方がわかる。店やメニューの選び方、昼の時間、食べる順番など、ひとつひとつに理由やこだわりがあって、業務とは異なる側面からその人の人間がわかる。だからどうしたという話もあるけれど、同じ船にのっている仲間のことなのだから、知っておいて悪いことはない。誕生日プレゼント、といって河原さんが溜まったスタンプカードをくれた(12回行くと1食無料になるそうだ)。
29日(水)版元ドットコム新年会。今回も総合司会をする。今年のイベントは印刷会社さんのトーク。特徴ある3つの印刷会社が集まり、自社の強みを話したり、参加版元からの質問に答える形で進む。私たちの印刷を一手に引き受けてくれている精文堂印刷の西村社長も登壇してくれる。印刷会社と一口にいっても、それぞれ特徴も得意分野も違う。さらにいえば営業担当者の個性も違う。複数社の話を聞き、改めて日頃どれだけ精文堂印刷さんのお世話になっているかわかり、感謝の気持ちを深めた。お世話になるばかりでなく、少しでも増刷率を高めて利益を出してもらえるようになりたい。トーク終了後は60名近くで懇親会。
31日(金)朝、何やら河原さんが興奮している。「近代出版研究」4号の紀田順一郎特集に、荒俣宏さんから3万5000字の原稿(予定分量超え)が届いたのだとか。ページ数が増えても、満を辞して大特集号にしようと喜びあう。末日で金曜日。あっという間に今年の1ヶ月が終わってしまった。『鎌田慧セレクション3日本の原発地帯』発売日。反原発運動は、冤罪問題と並んで鎌田さんの代名詞だ。4巻はさようなら原発運動。3月にかけてこれらをしっかり販売していかなくては。
今月読んだ本では、何といっても『新宿をつくった男』が面白かった。父や叔父がテキヤ稼業を継がなかった理由(そもそも親子間で世襲する類の生業ではない)もわかったし。尾津をヒーローともせず、ヒールともしない。商売人の顔とやくざ者の顔、両方の顔を持ってゆらゆら揺れながら(当人の主観としてはおそらく矛盾なく)生きていた人物像が描かれており、読みでがあった。さて、あと1か月で2024年度も終わりだ。
【おもな登場人物(登場順)】
藤巻さん 弊社創業者 むかしばなし、などぜひお読みください
笹森さん 弊社営業部長 自転車ガチ勢
河原さん 弊社データベース部部長。 『近代出版研究』4号がもうすぐ出ます
楠本さん 弊社編集者 直近の担当書は『二代男と改革娘』、もうすぐ『パレスチナ、イスラエル、そして日本のわたしたち』が出ます
亮一さん 弊社デザイナー 面白いTシャツ好き
Iさん 著者のパートナー 釣り好き