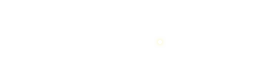第6回 本好きはうつへと至る一里塚
■『双極II型障害という病 -改訂版うつ病新時代-』内海健著、勉誠出版、二〇一三年
読了 2014/4/30
目次 http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100228
「改訂版あとがき」に拠れば、「本書の改訂にあたっては、第四章を「治療の指針」、第六章を「混合状態」として改稿し、その他の部分についても一定の加筆を行った。」「なお、タイトルについては、初版を出版したのち、他社より同一の書名の新書が出されたこともあり、今回を機に改変した」(p.243)。七年間で世間からの認知が進んだ所為もあらう。
双極II型を診断する要諦は、抑鬱状態そのものよりも軽躁病相を併せ持つかにある由(「第二章 軽躁というデーモン」)。以前読んだ春日武彦『問題は、躁なんです』(二〇〇八年)を想ひ出したが、本書では、躁が軽躁とは違ふ鑑別点(「転導性」=うつろひやすさの有無)も説かれてゐる。この複雑微妙な双極II型といふ病像を、既存の類型(単極型鬱病、躁鬱病=双極I型障害)の中間や折衷ではなく独自の疾患を成す「スペクトラム」として分析しながら何とか言葉で伝へようとする手際が、見もの。近年の「臨床哲学」だの「臨床社会学」だの言ふ便乗と違った本業の臨床的な思考とはかういふものか。まあ、初版で「精神科医からのメッセージ」を「「精神科医へのメッセージ」という名のシリーズと勘違いし」て書き出されたと言ふから(「あとがき」p.239)、臨床医向けになってゐるのかも。
薬物療法に関説して曰く、「臨床家の一人として言わせてもらえば、巷間エヴィデンスと呼ばれているものなど、それほど大層なものではない。膨大な数の症例を統計的に処理して得られた解像度の低いぼやけた所見が、臨床家の良識や知恵を凌駕するとはとても思えないのである。決定的な問題は、個別例を集積して一般的な所見を得るまではよいのだが、ではその所見を個別例にどう役立てるのか、この復路が見出せないことである。このことは、実際に患者を目の前にしてみれば明らかである。エヴィデンスとは、臨床家が独善に陥らないための参照枠と考えればよい」(「第四章 治療の指針」p.112)。「DSMに代表されるスーパー・フラットな診断の蔓延」(第五章p.136)への慷慨も散見される。エビデンス・ベースド医学批判といふか、臨床医学的判断力批判みたいな論考があったら読んでみたいもの。
「雑談、買物、酒、タバコが四大ストレス解消法」とは中井久夫『治療文化論』も言ってゐたが、本書は性差を論じて曰く、「少なくとも現在の日本の社会においては、軽躁がある個体をみまったとき、男性の場合の方がより適応的である」。「一つの理由として、個人の逸脱を受け止める社会や文化の仕組み」として「のむ、うつ、かう」が「逸脱や病理を吸収する装置として機能する」から。「それに対して、女性の場合にはせいぜい、「くう、かう、しゃべる」である。この場合、「かう」はもちろんショッピングである。実際、軽躁の病理をもつ女性は、しばしば過食や買い物依存に走る。しかし病気を受け止めるにはいささか物足りないかもしれない」(第二章p.43-44)。――ならば、今やこの社会はパターナリズムが薄れ女性的になりつつあるが故にメランコリー親和型性格に代って「マニー親和型」(第五章p.133)の軽躁(及びそこから転じての鬱)の病理が表面化したのだとしたら? 思へば男性の自分も、喰ふ・買ふ・喋るで軽躁状態になる以外に気鬱の発散法を知らぬ。消費社会の落後者なれば、「買ふ」はほぼ古本のみにて。いや多分に偶然に左右される古本漁りは幾分かギャンブルを「打つ」やうなものでもあるか。……「そして残されたのは、そのつどそのつどの強迫である。そこにはもはや揺るぎのない同一性はみられず、あるのは小さな差異の戯れである。[……]もはや強迫を方向付ける統制原理が欠けている。それゆえ、こうしたあり方自体がすでに不適応となる芽をはらんでいる」(終章p.223)。
森洋介
1971年東京生まれだが、転勤族の子で故郷無し。大学卒業後、2000年まで4年間ほど出版編集勤務も(皓星社含む)。2004年より大学院で日本近代文学(評論・随筆・雑文)を専攻、研究職には就かず。趣味は古本漁り。関心事は、書誌学+思想史(広義の)、特に日本近代で――それと言葉。業績一覧はリサーチマップ参照(https://researchmap.jp/bookish)。ウェブ・サイトは「【書庫】或いは、集藏體 archive」。
■書物蔵からひと言
図書館に就職する際に図書館学科の教員にこういわれた。「司書の職業病にうつ病があるんだよ」と。「なぜですか?」と聞いたら、「非営利組織は使命が抽象的で達成感が得られづらいし、目録作成は細かい作業だからなのでは」と言われた。
非営利はともかく、カタロギングは細かく単調だから、というのは閲覧部門から整理部門に異動した際にも地付きのカタロガーにも言われたことだった。私も後にうつ病診断されたことがあるが、これは特定の問題管理職が主因で――後にスキャンダルを悪化させたりもしてたな――管理職登用システムの構造的欠陥が背景にあり、そもそも整理業務とは無関係だった。同じ図書館でもレファレンス部門は毎回目先が変わるので、気晴らし効果があった。
日本近代書誌学を作ろうとした国文学者、谷沢永一もまた、重度のうつ病に苦しんだ人である。これらを考えると、司書や書誌学者の職業病としてうつ病が指定できそうだが、司書課程の教科書に出てこないのは困ったことである。森さんは中村古峡の雑誌『変態心理』(1917-1926)――今のことばで言えば「異常心理」。SexialなHentaiとはほぼ無関係――の復刻(大空社→不二出版, 1998-1999)に携わって以来、精神医学史にも興味があり、また書誌学者の職業病でもあるので、うつ病にも興味があるのだろう。書物研究のウラ主題がうつ病だとも言える。
森さんの恩師だった曾根博義先生も「ぼくはうつ病じゃないからホンモノじゃない(笑)」と言っていたというから、書誌学に傾倒した学者界隈では、職業病説があるのだろう。実際、私も2回ほど神保町の古瀬戸で曾根先生と楽しく古本談義をしたが、明るく楽しく気持ちよい人であった。
その谷沢の半自叙伝『私の「そう・うつ60年」撃退法』(講談社, 2003)は、うつ病の書誌学者の闘病記でもあった。うつ病を治す(?)のに、自宅からテレワークで大学の学内政治に熱中するさまなどがオモシロく書かれていた。書物ずきは一度、他人事としてなりとも読まれると参考になるだろう。
森さん書評に「多分に偶然に左右される古本漁りは幾分かギャンブルを「打つ」やうなものでも」とあるが、私が元気を出すのに使ったのは古本市だった。本当は、古本探求者側の知識など、主体性にかなり影響されるのだが、「掘り出し」というのは、多分に自分の「運の良さ」を実感させてくれるものである。世俗の賭け事――競馬競輪パチンコスロットルなど――はまるきしやらないが、週末古本展がよいは、たとえもうあまり買わなくなったにしても、やめられない止まらないといったところ。
また、京阪方面で行われる大規模な古本まつりに繰り出して、旅行趣味を多少なりとも持つようになったのも良かったことである。特に、80万冊の本を一度に展覧する夏の「下鴨納涼古本まつり」は、国会図書館員だった森見登美彦の創作中によくでてくるように、大変にインパクトのあるもので、気散じにはもってこいだ。
あたかもよし、皓星社から発売されたばかりの『古本マニア採集帖』は、コレクター36人の半自叙伝だけれど、著者南陀楼さんの方針で、濃ゆいマニアの手前の人たち、つまり世間と折り合いをつけて暮らしている人達(light maniaというべきか)が採録されている。病膏肓に入らぬように、参考にするとよいだろう。
友人代表・書物蔵識
(Twitter:@shomotsubugyo)
☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。