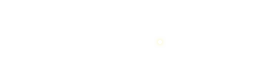第2回 あやふやなまなざしを見つめる(映画監督 住本尚子さん)
今年の6月、雨が降ったり止んだりしている中、自主的に製作した映画『ふゆうするさかいめ』を新人監督として池袋シネマ・ロサで上映した。映画館で上映することはわたしの夢であり、やっと「わたしは表現したいものがある人間なんです!」と多くの人に言えるような気がした。けれど、なんとなく自信が持てないままだ。映画にもその弱さが表れているようで不甲斐なくもあり、でもやってみなければ分からなかったこともあるし……という、第一歩とはこんなにも心細いものなのかと感じていた。
11月、名古屋シネマテークにて映画を上映することとなり、舞台あいさつに向かった。その時にたまたま愛知芸術文化センターで「第 25 回アートフィルム・フェスティバル」が開催されていて、ずっと見てみたいと思っていたストローブ=ユイレの『セザンヌ』(1989年)という映画を観ることができたのだ。
ストローブ=ユイレという作家を説明することはちょっと難しい。ジャン=マリー・ストローブとダニエル・ユイレの連名であり、夫婦でもあるおふたり。原作を脚色し作られる作品が多いものの、原作の内容を映画化する訳ではなく、テキストを原文のまま忠実に用い、映画にするからといって台詞を付け足したり、元々あるテキストを変える事はない。ストローブは「(…)物語は映像によって語られるのではない。サイレント映画が映像で物語ろうと試みたことは決してなかったし、そんなことできやしなかったのだ。(…)」(『ストローブ=ユイレ シネマの絶対に向けて』)と語り、映像については「ただ光の変化や作用を記録することであり、それはもはや物語とは無関係なものだ」と言っている。そう、ストローブ=ユイレ作品の物語と映像は別ものなのである。映画作りに対して非常に厳格で、スタイルを確立している誠実な作家の作品を観ること自体、背筋がぐっと伸びる。映画『セザンヌ』では、タイトル通り画家のポール・セザンヌについて描かれる。セザンヌもまた生涯をかけて自身のスタイルを築き上げ、キュビズムなど近代の絵画に大きな影響を与えた非常に厳格な人物だ。
映画『セザンヌ』は、詩人ジョワシャン・ガスケの著作『セザンヌ』(2009年、岩波書店)に含まれるセザンヌの発言の朗読に重ねて、セザンヌゆかりの土地やセザンヌの絵が映し出される。わたしはストローブ=ユイレが『セザンヌ』という本から取り出したテキストにとても感銘を受けながら観ていた。セザンヌは「すべてが有機化される。木々、野原、家々。私はそれを目にする。色斑を通じて。地層、下塗り、素描の世界は崩壊し、流れ去る。まるで大災害だ。(…)もはや色彩しかない。その色彩の中にあるのは、輝き、色彩を思考する存在、大地の太陽への上昇、それらの深みから愛へと向かう発散だ。」『ストローブ=ユイレ シネマの絶対に向けて』)と語る。彼は目の前にある色彩を写しとることに向き合い続けた作家だと感じるし、ストローブ=ユイレの作家としての姿勢も同じく、テキストをそのままに、存在しているモノを尊重することにとても真剣なのだ。
わたしは一体何に真剣に向き合っているのだろう? 映像に、そして絵に起こすときにわたしが大切にしているもの。はっきりと言えるのは、不確かなものがこの世の中に存在していることについてなのだが(初長編作品『ふゆうするさかいめ』と初短編作品『オとセとロ』(2016年)というタイトルからも分かるように、白黒はっきりしないもの)描きたい内容はあやふやなものだとしても、あやふやなものを映像として表現することは難しい。なぜなら対象を常にはっきりと写しとることを目的としてしまうし、絵に描こうとするならば、まず、線でモノのさかいめを作ってしまうからだ。いや、わたしはもやもやとした存在が撮りたいわけではなくて、存在しているモノに対するあやふやな“まなざし”を撮りたいのではないか。多木浩二著『眼の隠喩 視線の現象学』(2008年、筑摩書房)という本に、“まなざし”とは単に視線のことではなく、モノをみるにはそれまでの文化的な背景が存在するのだと書かれている。著者は、人種差別の背景にギリシャ人がインドやアフリカなどの見知らぬ土地に怪物をイメージしたことに触れ「(…)怪物を生みだすことは、かれらが世界を自分たちの世界とそうでないものに分離し、世界を一種の隠喩的地理学としてテキスト化することにほかならなかったのであり、(…)みずからのアイデンティティにとって根本的に重要だったのである。」と表現している。わたしたちの周りにはいつの間にか人種や性別、価値観などの違いにより分離された空間があり、どちらかに振り分けられない感情やものごとがあるにもかかわらず、無視されてしまう時がある。何か生きづらいと日々感じる瞬間には、なにかしらの“まなざし”が存在しているのだと思うようになった。その“まなざし”の正体をわたしは追い求めているのではないだろうか?
しかし、わたしにはまだ “まなざし” を視線でしか捉えることが出来ていなかったように思う。アニメーションを用いたり、夢と現実、もしくは互いに見えているモノが別であるということを表現するために、ひとつの時間軸にいくつもの視線の先を並べたけれど、なぜ登場人物たちが別々のモノを見てしまうのかは上手く表現できていないかもしれない。けれど、互いにこの世界から切り取る視点が違うからこそ、映像も滑らかにつなげるよりは、ちぐはぐに留めておきたい。だからこそ、ストローブ=ユイレが全くの別物であるテキストと映像を、共存しているように表現することはわたしにとってもとても自然と思えるし、一見分かりづらいと思われることをストイックに探求し続けている姿勢に惹きつけられているのだと思う。
映画『セザンヌ』を観てから、よりセザンヌのことが知りたくなり、ガスケの著作『セザンヌ』を買って読んでいる。映画では、本の中にある「第二部 彼が私に語ったこと」の「第一章 モチーフ」というパートのうちセザンヌが実際に話した言葉をそのままガスケが記したとしている箇所からの引用が多い。雑誌の対談みたいに書かれているので、まるでさっき話していたみたいな臨場感があって面白いし、「第一部 私の知ることやこの目で見たこと」の「第一章 青春」も、いかにセザンヌが震えるように感受性が強く、それ故に理性と取っ組み合いをしていたかが語られていてとても興味深い! そして改めて思うのが、ガスケから見えるセザンヌの魅力的な部分は、この映画『セザンヌ』からは読み取れないということだ。何かを描かないということは、何かを失ってしまう。
初めての長編映画作品が映画館で上映されること自体、わたしは恵まれていると思う。と同時に、映画は自主映画といえども、映画館で観るに値するのかを観客からふるいにかけられることでもある。レビューを見るたび一喜一憂してしまうのは、わたし自身が何かを選び、何かを失うことを本質的に理解できていなかったからなのではないか。わたしにこれから必要なことは、“まなざし” の探求と、選び取ったモノへの自覚だろう。自信を持つには時間がかかるかもしれないけれど、少しずつ、じっくり向き合っていきたい。さぁ、長い長い作品作りの第二歩を踏み出していこう!
参考資料:渋谷哲也編『ストローブ=ユイレ シネマの絶対に向けて』(2018年、森話社)、多木浩二著『眼の隠喩 視線の現象学』(2008年、筑摩書房)、ジョワシャン・ガスケ著『セザンヌ』(2009年、岩波書店)
住本尚子(すみもと・なおこ)
映画『ふゆうするさかいめ』は2022年2月6日(日)14:30〜シネマノヴェチェントにて1日限定上映!上映後には、矢崎仁司監督と風間志織監督、そして住本尚子さんによるトークショーがございます。詳しくは公式Twitter(@fuyusurusakaime)やinstagram(@fuyusurusakaime)をご覧ください。
☆本連載《よめば羊もよってくる》は皓星社メールマガジンにて、隔月で更新してまいります。ご登録はこちらよりお申し込みください。