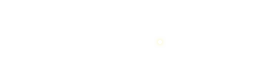第3回 貧しき中にも読書あり――アガンベン『いと高き貧しさ――修道院規則と生の形式』
■ジョルジョ・アガンベン『いと高き貧しさ 修道院規則と生の形式』上村忠男・太田綾子訳、みすず書房、二〇一四年十二月
読了 2016/2/2
目次:http://www.msz.co.jp/book/detail/07853.html
「Ⅲ〈生の形式〉」、就中「3 いと高き貧しさと使用」で、「瀆神礼賛」(『瀆神』月曜社、二〇〇五年九月、pp.119-121)で閃かしたフランシスコ会による所有と使用の区別論を詳論する。併せ読む。
Cf. http://www.sociallibrary.jp/entry/4901477196/
何を読んでも、書物関聯の記述に目を止めてしまふのは読書人のさがである。脇筋ながら、中世修道院における読書史に関してメモ。
「メディターティオー(meditatio)」について。「ハインリヒ・バハトは、この用語は近代的な意味での「瞑想/沈思黙考」を指すのではなく、もとはレクティオー(lectio 朗読)と区別されたものとしての聖書の暗唱(一人で、または共同での)を指していたことを示した」(Ⅰ「1 規則の誕生」1・10、p.33)。これは音読から黙読へといふ読書の歴史の基本傾向に重ねて見られる。「四世紀以降、沈黙の読書の習慣が広まっていったことはよく知られている。アウグスティヌスは、師のアンブロシウスがそうしていることに驚いている。[……]メディターティーオーは、もはやレクティオーを必要としなくなったこの実践を受け継ぐものだった。なぜなら、テクストはいまでは不断の、そして一人でもできる朗唱のためにすでに暗記されていて、修道者の一日の伴をし、内面から時を刻み、彼のあらゆる所作、あらゆる活動と不可分になっているからである」(p.34)。「「時の測定 perpensatio horarum」と「暗唱 meditatio」は、カントの発見よりはるかに遠い過去において、時間が内感の形式に転化するための二つの装置だったのだ」(pp.34-35)。読むことは考へること也、特に物質的書物から離れて心内に刻まれた書を読み上げる時は。
「クレルヴォーのベルナルドゥスの『修道院の階段』では、「それをとおして修道士たちが地から天に上げられる階段」は四段からなっている。「固めの食べ物を口に運ぶ」朗読(lectio)、「それを噛み砕く」暗唱(meditatio)、「味を噛みしめる」祈り(oratio)、「安らぎと喜びを与える甘さそのもの」である観想(contemplatio)である」(1・11N、p.36)。——食物による書物の比喩、共に口を使ふ食事と読書(まだ音読なので口を動かすのだ)の類比は、メアリー・カラザース『記憶術と書物 中世ヨーロッパの情報文化』第五章「記憶と読書の倫理」中「消化瞑想活動としての読書」(工作舎、一九九七年十月)やイヴァン・イリイチ『テクストのぶどう畑で』(法政大学出版局、一九九五年一月)が想起されよう。日々食べるやうに、読め。——「のちにフランシスコ会士たちがヨハネス二十二世に反駁する議論のなかで出てくるように、飲むとか食べるということは、いっさいの法律的意味合いを欠如させた純粋に事実的な人間的実践のパラダイムとなっている」(Ⅲ「3 いと高き貧しさと使用」3・2、p.167。Cf. p.177)。
また、ハンス・ブルーメンブルク『世界の読解可能性』(法政大学出版局、二〇〇五年十一月)への暗示的参照(引喩)と覚しき文も見られる。「ギュンター・バーダーは、修道生活が始まったころ、修道者や隠遁者を悩ます恐るべき悪、すなわち怠惰に対するとびきりの治療策が朗読(lectio)だったことを示した」(Ⅰ1・11N、p.36)……「ポントスのエウアグリオスが伝えるアントニオスの逸話では、怠惰を乗りこえた状態は、自然そのものが一冊の本となり、修道士の生が中断することのない読解可能性の絶対的な状態になった段階として提示されている。「ある賢者が義人アントニオスを訪問して言った、「師よ、どうして本の慰めなしでやっていけるのですか」。「わたしの本は」とアントニオスは答えた、「被造物からなる自然で、それはわたしが神のことばを読みたいときにはいつでもそこにあるのだ」。完成された生は世界の読解可能性と一致し、罪は読むことの不可能性(それが読解不可能なものになってしまうこと)と一致する」(1・11N、p.37)。読むことが人生であり、生きるとは世界を読むことであり、読めないことは罪悪なのだ! おお何とも読書人に訴へる言葉であることよ。
「Ⅱ 典礼と規則」中「2 口述と書記」2・3は、「『レグラ・マギストリ〔師たちの修道規則〕』〔六世紀前半、起草者不明の会則〕」(p.7)の第二十四章「食事中の毎週の朗読者について」を分析する。「この場合〔毎日規則を読むよう、朗読者に厳命する箇所を朗読する場合〕には、朗読と規則を実行に移すこととは、余すところなくただちに一体化する。彼に規則を読むよう指示する規則を朗読するとき、朗読者はそのままに、規則を行為遂行的に実行している。」(p.103)。統制的規則ではない、パフォーマティヴな構成的規則になるのだ。「口述と書記のあいだの弁証法は、ここでは完璧である。書かれたテクストがある。だが現実には、それは書かれたテクストからなるものの朗読をとおしてしか生きない。[……]規則は文書が前もって存在することを想定しているが、文書はそれ自体としては不活性であり、朗読をとおして「使用に移され」なければならないのである。同じことは、数頁あとでも、旅している修道士に朗読するよう、もしできないなら、「規則に関わることを、規則に取り戻させるために」、暗唱に頼るよう奨めることで、再び強調されている。レクティオー〔朗読〕とメディターティオー〔暗唱〕は二つながらに規則にとって構成的な要素をなしており、規則のあり方を定義しているのである」(p.104)。……さりとて、記憶頼みの暗誦と実際に文字を眼で逐ひつつ読むこと(黙読の普及しない当時は朗読)との一致は必ずしも保證の限りでない以上、いつかmeditatioは本文を反復する暗誦から逸脱して我自ら作する黙想へと化するのであらうが(古へに忠実であらうとして却って「自我作古=われよりいにしへをなす」やうな僭上沙汰に陥るのは、遠く明末清初の考證学成立期にも見られた逆説だ)。記述通り記憶通りに再現したつもりで独自の思考になってゆき、原文から乖離して、それでも「読む」と呼べようか——しかし解釈学とはおよそさうした拡張読解の思想である。
さて本筋を読むことに戻って。
いつもながらイタリア人らしく御家藝のローマ法を参照するアガンベンの議論は、ロマニスト木庭顕の「占有 possessio」と「所有 dominium」とを辨別する法学的議論(##)にも繋げられさうなのだが、さういふ視点は出て来ない。
## 稲葉振一郎『インタラクティヴ読書ノート別館の別館』→改題『shinichiroinaba’s blog』2011-11-19「「占有」について」:http://d.hatena.ne.jp/shinichiroinaba/20111119/p1
十三世紀アッシジの聖フランチェスコに発する托鉢修道会であるフランシスコ会は清貧・無所有を旨としたが、その主張する所有することなき使用、「単純な事実上の使用(simplex usus facti)」とは、「法律家たちにはよく知られていた事実と権利、“quid iuris”〔権利上のことがら〕と“quid facti”〔事実上のことがら〕との対立が、一般的にだけではなく、まさに使用に関連して起きていること」を示す(Ⅲ3・2、p.167。Cf. p.184)。近代哲学でカント用語の事実問題/権利問題にまで響くことだ。これは本書内だと、前節「2 法権利を放棄する」を踏まへてゐるのは勿論、「中世哲学の用語でいうと、このことは、問題となるもろもろの現実は本質および“quid est”〔それが何であるかという意味での「〜である」〕の平面ではなく、たんに存在および“quod est”〔それが現実にあるかどうかという意味での「〜がある」〕の平面に位置しているにすぎないことを意味している」(3・6、pp.180-181)。「いわば実存主義的であって本質主義的ではない存在論」(p.181)、即ち、本質存在(essentia)よりも事実存在(exsistentia)、サルトル曰く実存は本質に先立つ、って奴か。また事実上の使用とは、言語行為論風に「規則が規制しなければならないはずの生を行為遂行的に実現しているようにみえる規則」(Ⅱ「1 生の規則」1・3、p.92)や、ウィトゲンシュタインの名と共に語られる「ある既存の事物の状態を規制したりするのではなく、それら自体がある行為や事物の状態を存在にもたらす規範」である「構成的規則」の問題(Ⅱ1・4、p.95)にも照応するわけだらう——尤も、統整的/構成的(regulativ/constitutiv)の対概念はウィトゲンシュタイン以前にこれまたカント以来の用語だったけど。さらに本書外だと、占有は権利でなく事実であると説く木庭顕(###)をも聯想させる。
### 『ともの読書日記』2013年11月11日「ボアソナード民法から読む木庭顕「占有理論」」:http://tomonodokusho.cocolog-nifty.com/blog/2013/11/post-dfb6.html
木庭も特筆するサヴィニー著„Das Recht des Besitzes“(『占有の法』乃至『占有権論』一八〇三年)はアガンベンも引證する(Ⅲ3・7、p.185)ものの、この上村忠男・太田綾子訳は占有に当る語を「“possesio”〔所持〕」として「物を所持すること自体は、その原初の概念からすると、たんなる事実である」等と訳すので、これが法学上は占有論だとは解るまい。本書で「占有」は所有に次いで「借用」と並べて触れるくらゐ(Ⅲ3・1、p.163)。それではジョン・ロックから本邦の川島武宜に至るまで近代思想の土臺に置かれた「所有」に囚はれてしまふ。実際アガンベンの行論では、所持=占有は所有と対立せず、むしろ所有権を成立させる前提としか見做されない。「使用の事実的性格は、それ自体としては、それが法権利の外にあることを保証するのに十分ではない。なぜなら、どの法権利も事実的側面を含みもちうるように、どの事実も法権利に変容しうるからである。」(3・7、p.186)……「フランシスコ会士たちは使用を法律的用語でもって正当化することに心を砕いていたため」(3・8、p.186)、「彼らはますます法的概念の圏域に巻きこまれていき、最終的にはそれに凌駕され敗北することとなるのだった」(3・7、p.186)。なればこそ「修道院規則が法律的性質をもつか否かという問題はアナクロニズムに陥ることなくしてはほとんど提起不可能である」(Ⅰ「2 規則と法律」2・9、p.61)と却けられ、「たんに法権利に対して否定的な性格をもたされて終わってしま」(Ⅲ「閾」p.194)うのではない「生の形式」そのものを定義すべき主題に据ゑることが提言される。とは言へ、法学の範囲内でもまだまだ議論の餘地はありさうだ。アガンベンも「それでも、修道院の規則には法律的文書と見なしうる面もある。が、それは民法や刑法ではなく、公法に関連する」(Ⅰ「3 俗世からの逃亡と創憲」3・1、p.65)とは言ふ。では、公物法論で公共物(国や公共団体が自用に所有する財産)と区別される公共用物(道路・河川・公園など一般公衆の共同使用に供されるもの)を、木庭顕流に、多数で占有して取り分けることができる「みんなのもの」ではなく「誰のものでもないもの」(誰も占有しえない)といふ公共的な物(res publica)(####)として見るならば、その公共用物の使用は所有/占有概念から如何に考へられるか。法思想史とかで誰かやってくれてないのかしらん。
#### haruhiwai18『もちつけblog・はてなブログ版(仮)』2019-07-21「自己利益を厳密に計算する思考なしに真の信頼は築きえない −木庭顕『法学再入門 秘密の扉—民事法篇』を読む−」:https://haruhiwai18-1.hatenablog.com/entry/2019/07/21/123000#fn-514fb24d
読書人に引きつけて例示すると、公共用物として使用できるのは図書館の蔵書であり、利用者には所有できないが占有し得るもの(他の利用者に借りられてその一時占有下にあれば使用不可となる)。無料原則によって貸出する図書館でもコピー機利用には課金するのは、情報の移転に際し複写したコピー紙は個々の利用者の私的所有物になるからだらう。アガンベンによれば、使用不可能にする分離(宗教的に言へば聖別)は現代では博物館といふ展示の場が典型的だ(『瀆神』p.122・131)。秘仏開帳よろしく、博物館・美術館の収蔵品は展示場で見せるだけで使用させない(貴重書が展示品となる場合、ページめくって読むことは禁じられてゐる)。が、博物館的施設でも附属図書室等の図書資料は公衆の閲覧・調査用に供されるし、図書館ならなほのこと。しかるに二〇一〇年代以降の電子書籍になると、電子化した媒体へのアクセス権を販売するがその所有権は誰にも渡さないといふ形式が増え、一般にソフト・アプリ類もディスク所有させないダウンロード・レンタル契約が主流となった。この場合、ゴーイング・コンサーン(継続企業の前提)が不動産みたいに見込まれてゐるけれど、浮き沈みある事業の持続力次第で作品(ハンナ・アーレントの言ふ「仕事 work」)の永続性まで弱められる危ふさがある。事実、このサービスを通じて購入したコンテンツは配信元が無くなったら以後使用不能になりかねない(#####)——積ん読(ストック)や貸し借り(別の人に使用させたり使用させて貰ったり)の自由が所有制限に伴って奪はれてゐるのだ。知識や情報そのものは有体物でないだけに、飲食等の使用と共に無くなる消費財は所有無しには使用もできぬと言ふフランシスコ会批判があった(Ⅲ3・4〜3・5)のと同様、分離した把握が難しい。著作権も、英米法流のcopyright(複製権)としてよりも専ら大陸法流にauthor’s right(著作者の権利)と捉へられれば所有者の物財であるかのやうに権限が握られ、使用する側の自由が束縛されゆくばかりとならう。
##### デイヴ・リー「マイクロソフトが電子書籍事業を廃止、本は消滅……デジタル時代の「所有」とは?」『BBCニュース』2019年4月5日
Cf. https://twitter.com/livresque2/status/691892395814821888
フランシスコ会修道士達がもと「小さき兄弟たち」と自称したのは、「法律的見地からは「他権者 alieni iuris」であって、「自権者 sui iuris」である大人の後見下にある「家子 filius familias」や「未成年者 pupillus」と同等にみなされる」(Ⅲ2・2、p.148)、つまりは家長でも相続人でもない子供の意味であったらしく、江戸期武士風に言へば「部屋住み」、太宰治の津軽辯だと「オズカス」(叔父糟)みたいだが、そんな家の厄介者らとて所有能力こそ認められないものの親の財産の使用に与ることで生きてはゆけた。本来、貧しき者・持たざる者・所有し得ぬ者ですら使用は許されてゐたのに、占有が所有に先立つことを忘れ、所有権から使用一切をも律しようとするから無理な歪みが生ずるのではあるまいか。権利=法以前に使用の事実がある、その剥き出しの生の事実を所有といふ色眼鏡を外して視るには、また別の視力補助具(「占有」概念とか)が要るのだらう。「そしてもし使用を、所有に対して否定的にのみ定義することをやめるとしたなら、使用とは何なのだろうか。」(Ⅲ「閾」、p.195)。さう、読書史で言ふと、碌に本が買へない貧書生でも立ち読みや廻し読みはできた事を視野に入れなくては、何がどれだけ読まれてゐたかの実態には迫れないやうに(?)。「どのようにすれば、使用——すなわち自分のものとして所有できないものであるかぎりでの世界への関係——を、エトスおよび生の形式に変換することができるのだろうか」(p.195)——世界が書物として読解可能なやうに、また、生きることが読むことであるやうにして……? 本書も、借覧で済ませた。
森洋介
1971年東京生まれだが、転勤族の子で故郷無し。大学卒業後、2000年まで4年間ほど出版編集勤務も(皓星社含む)。2004年より大学院で日本近代文学(評論・随筆・雑文)を専攻、研究職には就かず。趣味は古本漁り。関心事は、書誌学+思想史(広義の)、特に日本近代で――それと言葉。業績一覧はリサーチマップ参照(https://researchmap.jp/bookish)。ウェブ・サイトは「【書庫】或いは、集藏體 archive」。
■書物蔵からひと言
この本、ちょっと読む人を選ぶ。思想史慣れしているか西洋中世史をやった人ならオモシロさがわかるだろうけれど。200ページ強しかないのに、5000円越えの値段、やっぱり、みすず書房でないと出せないよなぁ……。それはともかく。
この本の主題は中世修道院のスケジュールぎっちぎち生活の話なんだけれど、それらが全部、規則化(文章化)されているので、逆に規則書を見れば生活全体やその一部、とりわけ、本来分からない内面心理まである程度わかるよ、というもの。
森さんは本書でも本好きの興味に引きつけて読解していて――そこがわちきに有り難いところなんだが――読書、特に音読/黙読問題への手がかりが書かれているのに注目している。
修道院生活では「レクティオー(lectio)」という動詞が聖書の音読(朗読)、「メディターティオー」(meditatio)が聖書の暗唱という対比があったという。しかし、メディターティオー(暗唱)は、テキストが眼前にないがゆえに、独自思考を黙ってすることに発展していってしまったという(暗唱がいつのまにか観想になった)。
暗唱は〈暗記したテキストを、声に出して〉読むこと、なわけだけれど、これが〈暗記していないテキストを、声に出さずに〉読むこと(黙読)と隣接する行いなのは、直感的にわかることかと思う。暗記したテキストは声を出さずにココロで読むことが容易にできるからである。「メディターティオー」は、観想、沈思黙考に転化していくが(英語のメディテーション)、その過程で、テキストをココロの中で読み上げる(黙読する)ことを自然発生させた可能性がある(んではないか、というのが森さんの読みね)。
森さん感想文後半で出てくる「ポセッシオ」(占有)と「ドミニウム」(所有)については、著者アガンベンが論じていない言葉分けだけれど、
本好きなら憶えていよう、往年の名画『薔薇の名前』(1987年日本公開)で修道僧同士が会派に分かれて、イエスの持っていた財布はイエスの私物だったかで激烈な神学論争をしていた。主人公の師匠、ショーン・コネリーが演じたバスカヴィルのウィリアム――作中で探偵ホームズ役だ――は、フランシスコ会修道士だったことを思い出す。
アガンベンは所有権を認めないフランシスコ修道会で提唱された使用権(いや、使用の事実)の議論をしているけれど、森さんはむしろここには木庭顕流の新式ローマ法論を持ち込んで、占有の事実から権利義務を考えるほうが筋がよい、と言っていて、例えばそれは、なぜ図書館で本を借りる際にはタダで、本をコピーすると有料なのか、といった議論にも敷衍できると、これまた本にひきつけた読みをしている。
国会図書館で、所有権は国(具体的には財政法により衆議院議長)にある書庫本を出してもらって閲覧するのは占有で、だから貸付返却ごとに貸借契約データを残さないといけない。けれど、閲覧席で座る椅子、専門室にあるレファ本は占有でないので(物品管理法における「処分」でなく「供用」となり)貸借契約データを残さない、なんて議論にも展開できますな。
友人代表・書物蔵識
(Twitter:@shomotsubugyo)
☆本連載は皓星社メールマガジンにて配信しております。
月一回配信予定でございます。ご登録はこちらよりお申し込みください。