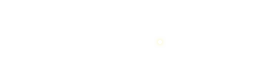むかしばなしⅡ
根拠のない自信を持って30歳で出版社を始めたものの、経営の訓練を受けたわけでもなく資本も人間関係も乏しいままだったから、困難は約束されていたようなものだった。始めて数年で行き詰まった。負債は雪だるま式に膨らんでいて千万単位に及んでいた。立ち止まって40歳までに負債を整理しようと決心してまぁいろいろやりました。
この時期、訪問販売の「株式会社図書月販」、後の「株式会社ほるぷ」の残党や類似の販売方法を採る「書籍販売会社」が残っていて、夢よもう一度と蠢いていた。ほるぷの全盛期には月商一千万単位の伝説の販売員もいたという話だ。高度成長の真只中で、新築の応接間の飾りに百科事典が飛ぶように売れた時代だ。(今ではその百科事典というジャンルがジャンルごと無くなってしまった)最近でも古本屋で『名著復刻全集 近代文学館』のバラを見ることがあるがその名残だ。当時は既にブームは去っていたが、一部の出版社は高額なセット物を企画して企画書一枚で販売会社から手形を受け取って資金繰りに回していた。
販売会社は中身はどうでも商品さえあれば「売る」自信があったんだろうね。どういう売り方をしていたのかは見たことはないが、パンフレット一枚で割賦支払いの契約書にはんこ押させれば一丁上がりだ。今のようにクーリングオフの制度もなかった時代で、ラメの入った背広なんか着ていた人たちもいた業界だ。出版社の経営者は、そういう人たちを相手に期日までに商品を仕上げなくてはならないから文字通り必死だった。そんな企画の幾つかを絶対に期日までに仕上げる契約で受けたこともあった。その会社の社員は毎日遅くまで仕事をしているのだが、一向に進展がない。力任せになんとか仕上げましたよ。そこはサラリーマンと手負いの一匹狼の気迫の差です。後に某図書館でその時手がけた本を見たときはギュッと目をつむって足早にその棚を離れたのは言うまでもない。図書館の名も書籍のタイトルも絶対に言わないよ。
書籍販売に関し、取次-書店といういわゆる「正常ルート」以外の様々な流通ルートがあることを知ったのは後に役に立った。取次が絶対の力を持っていた時代。しかし、「正常ルート」ってどれだけ上から目線だろうね。ほかは「異常ルート」というのだろうか。
「融通手形(融手)」の怖さを知ったのもこの頃だ。銀行融資が受けられないなど資金繰りに窮した同士がお互いに同期日、同金額の手形を振出して交換する。それを割引たり支払いに使う事によってその額の資金調達をすることができる。「馴合手形」とも言った。一種の信用創造ですかね。期日通りに引き落とせばいいが、相手が落とせないと相手と自分の手形の両方を決済しなくてはならなくなる。銀行融資を受けられずこんなことにまで手を出すのだから両方引き落とす余裕が有るわけはない。行先は連鎖倒産だ。だからこの手形だけは何にも優先して引き落とすのが「仁義」だ。生死を共にするのだから融手仲間の結束は固くまさに「親の血を引く兄弟よりも固い契」の「兄弟仁義」の世界だ。しかしそれでも、ダメな時はダメな悲劇も見た。そういう世界も身近にあった。だから再出発後は一切当座取引はしていない。
この時期、創業から10年間、ほぼ1980年代に重なるけれど、僕の「黒歴史」であまり語りたくないのだ。そして40歳からまた性懲りもなく再出発した。会社自体はほそぼそと続いていたけれどね。
既述のようにハンセン病関係の出版をすることになったのは、村松武司(1924-1993)の影響だった。村松は「京城」うまれの三代目植民者。帰国後、大江満雄、鶴見俊輔、井出則雄らと出会う中で「ハンセン病」とアジア、殊に「朝鮮」という二つの中心を持つ楕円を自らの思想の核に据えた特異な詩人・思想家だった。また、長年「数理科学」の編集長を務めた編集者でありその表紙を長く担当した安野光雅との交友も特記すべきだろう。安野のエッシャー張りの画風は数学と物理学と哲学の学際的なこの雑誌の表紙を担当したことが大きく関係していると思われる。
「黒歴史」中の1980年代の半ばころ、新聞紙上で「われわれの文学全集が欲しい」という、ハンセン病回復者の作家・島比呂志の一文を目にして、「よし、いつかやってやろう」と思った。ハンセン病作家では、小説の北条民雄、歌人に明石海人、俳句では村越化石など一般の文壇・歌壇にいても一家をなす人がいてその層は厚いといわれていたが、その全貌は必ずしも明らかではなかった。そこで、全国の療養所の作家たちの著作目録を作ることから作業を始めた。現在のように「国立ハンセン病資料館」もなく、全国に散らばるハンセン病療養所の資料から目録を作成することは、何年もかかる仕事になりそうだった。
ハンセン病患者・元患者の著作目録作成は2000年までにほぼその作業を終えた。この作業は村松の相弟子の能登恵美子が熱心に取り組んだ。目録作成の過程で「ハンセン病図書館」(多磨全生園)をつくった山下道輔さんや「神谷書庫」(長島愛生園)を守る双見美智子さんなど、自分たちの資料は自分たちで収集管理しようとする入所者の存在も知った(村松武司も島比呂志も能登恵美子も山下道輔も双見美智子もういない)。
1925年ころから2000年までに出版された作品集は、個人や合同作品集合わせて1000冊以上に達していた。
さて、再出発したものの資金もなくほそぼそと手間賃仕事などをしながらどうしたものかと考えて時を過ごしていた。折しも1953年に始まったテレビの民間放送が40周年を迎えようとして、記念事業の機運が盛り上がっていた。学生時代家永三郎さん(私の出た学校は、先生でも面と向かって「さん」づけが慣わしだった。慶応の掲示板は諭吉以来の伝統で教授でも「○○君休講」などと掲示されると聞いたが今はどうか?)が高く評価していた水野広徳の著作集出版を「記念事業」として水野の生まれ故郷・愛媛県の南海放送に提案して採用された。
水野広徳(1875-1945)は、海軍兵学校出身で日露戦争の旅順港封鎖作戦に従軍。少年の日に「強きをくじき、弱きを助ける侠客に憧れた」という人である。同じ愛媛でも司馬遼太郎の『坂の上の雲』の秋山好古・真之兄弟は水野の一回り先輩になる。その海戦記『此の一戦』(博文館 1911)がベストセラーになり、その印税で第一次世界大戦を観戦にヨーロッパに行った。そこで見たのは、日露戦争のように無人の荒野で兵隊同士が戦たり公海上で戦艦が大砲を撃ち合うのとはまったく違う戦争だった。第一次大戦は航空機(飛行機・飛行船)・戦車・潜水艦・毒ガスなど核兵器以外の近代兵器が出揃った戦争だった。水野が眼にした戦争は、航空機による都市の空爆あり、潜水艦の商船攻撃あり、非戦闘員を巻き込んだなんでもありの総力戦だった。国際紛争を解決する手段として戦争してはダメだと「日本国憲法前文」のようなことを考えた水野は、帰国後海軍を大佐で退役し軍縮・平和のために論陣を張るようになった。
しかし、水野は敗戦の年の秋になくなり、先行研究も皆無に近いところから、まず作らなければならない著作目録の作成は困難を極めた(また目録だ。目録ばっかり作っていたんだね)。なぜならば、1930年頃に日本で出版された定期刊行物は約4万タイトルといわれるのに対し敗戦の年(1945年)には統廃合によって2000に減じ、多くは敗戦とともに廃刊となっている。戦後に生まれたわれわれ(僕も一応戦後生まれなのだ)は、戦前の雑誌の名前も知らず、その中から水野の記事を探し出すのは、地図も磁石も持たずにジャングルに分け入るようなものだった。NDLの「雑誌記事索引」も民間のデータベースも、検索対象は「戦後」に限られ(そもそもGHQの勧告によってNDLができたのが戦後の1948年だ)われわれの目的をかなえてくれるものはなかった。
そこで結局、その地図に当たる「記事目録」を探すのがもっとも効率的と考えた。すると、むしろ戦前期のほうがこうした目録類はたくさん作られていることがわかった。ただ、その多くは学術雑誌などの巻末に「先月の重要記事」などとして掲載されているため埋もれてしまっていたのだった。
また、台湾総督府、満鉄総裁(満鉄調査部)、東京市長(東京市政調査会)など赴任する先々で、大掛かりな目録作成事業を行った後藤新平の一面や、戦後、靖国神社の宮司になってその在任中、A級戦犯の合祀に頑として応じなかった筑波藤麿は、昭和のはじめから敗戦のときまで私財を投じて毎年『昭和○年の国史学界』という目録を作り続けたことを知った。筑波藤麿は、いわゆる「鳥の宮様」山階芳麿の異母弟に当たる元皇族である。後に目録の著作権のことでお目にかかった早稲田大学教授の筑波常治先生は、藤麿の長男に当たるが、「私は天皇制には反対です」と明言された。先生は、「思想の科学」の同人で、学生のころ誌上で何度もお見かけしたことがあった。筑波さんは農業技術史が専門で「緑が人類を救う」と考えていたから服装は緑系統で統一していた。といってもケロヨングリーンのような奇抜なものではなくチャンとコーデネイトされていたから違和感は無いどころかおしゃれだった。頂いた名刺が再生紙で緑のインクはまあそんなものかと思ったが、住所がM市緑町となっていたのにはたまげた。もし緑町にグリーンマンションなんてのがあったら迷わず買ったに違いない。
同じ元皇族でも明治天皇の裔と称するあの竹田親子の下品さとは大違いだね。
余談だが「緑のおじさん」はもうひとり知っている。秋山正美という作家(?)にして古本コレクターだ。「薔薇族」の編集長だった伊藤文學の回想によると、「薔薇族」創刊以前、実家の第二書房を手伝っていた1965年頃、靴もスーツもネクタイもシャツもすべて緑の風変わりな男が原稿を持ち込んできた。原稿には「オナニーの正しいやり方」と表書きがしてあった。伊藤はこれに『ひとりぼっちの性生活-孤独に生きる日々のために』(1965年)というタイトルをつけて出版し結構売れたらしい。伊藤の出版屋としてのセンスを感じる話。この風変わりの男が秋山なのだがぼくが知るのはずっと後のことだ。僕の知った頃は家も車も緑のペンキで塗ってあるという噂だった。しかし、これは本筋に関係ない。
こうして戦前期の雑誌記事目録のほとんどすべてを収集して、「水野広徳著作目録」は完成し、1995年に著作集は出版(まだ刊行する体力がなく、発行は雄山閣だった)にこぎつけることができた。
『水野広徳著作集』第6巻は「書簡・日記」編だが、一年分奇跡的に残っていた日記の1941年5月30日の条に「未知の人福岡市石賀修氏より揮毫依頼状」、5月31日「石賀修氏に承諾の返書」という記載がある。この時期は、良心的兵役忌避者で若い頃感銘を受けた『神の平和-兵役拒否をこえて』(1971年)の著者イシガ・オサムが憲兵隊に自首した時期と一致する。確認するとイシガの妹さんが「それは兄に間違いありません。兄は水野さんを大変尊敬しておりました。ただ兄は高齢で入院中でもありお目にかかるのは無理でしょう」と、お目にかかることはできなかった。「ご参考になるなら」と送っていただいた水野の色紙「戦傷の大和魂無知の勇 明知の勇は君にあり」は、今、社宝として会社の壁面を飾っている。ただし、この時の揮毫の色紙は家永三郎氏が所持していると主張されていた。弊社の色紙は紙も粗末で内容からも敗色の濃い戦争末期に書かれたものと推測される。
余談だがこの謹厳そのものの老歴史学者には刑罰の研究に端を発した秘密のコレクションがあると噂されていたがあれはどうなったのだろうか?
収集した目録は、約10万ページにのぼった。目録の威力を実感したわれわれは、『水野広徳著作集』に利用しただけで終わらせるのは惜しいと、整理して『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』(全120巻)として刊行した。この企画は販売をK書店とM社に持ち込んだ。両社とも評価してくれたがM社が総発売元・買取りを提案しそれに乗った。結果的に取引を蹴ったことになってK書店は激怒し、30年後の今日もこれがたたっている。当時の担当者は誰も残っていないのに引き継ぎがされているらしいのだ。怖いね。
ただし、これ自体は結構好評で『ハンセン病文学全集』刊行を経済的に支えてくれた。
これより先、1993年われわれのよき理解者であり指導者であった村松が死んだ。68歳の早すぎる死だったが、気を取り直して『ハンセン病文学全集』の刊行を急ぐことにした。
それでも後藤新平の孫に当たる鶴見俊輔氏や加賀乙彦、大岡信氏らを編集委員に『ハンセン病文学全集』の刊行を開始したのは、2003年だったが、完結したのは2010年7月で足掛け8年の生みの苦しみを味わった(この全集の編集は弊社近くの某大手出版社の社長の理解と援助を受けた)。『ハンセン病文学全集』はその母集団が多いときで数万人しかいないハンセン病の患者・元患者の作品集だが、そのような集団がこれだけに質量の作品を持つのは世界でも例がないといわれる。
『ハンセン病文学全集』の10巻は「児童作品集」で、ハンセン病療養所に幼くして入所した子どもたちの作品集だ。これは担当編集者・能登恵美子の強い主張で独立した巻になった。ここに「十時ころでした石賀先生が来られました。『高志君、石賀先生が来られているよ』と知らせますと、いままでじっとしていた高志君がきょろきょろしはじめしきりに先生を探しているのです」と瀕死の子どもが慕う「石賀先生」がいた。憲兵隊から釈放されてのちハンセン病療養所に勤務することを選んだイシガ・オサムとの3度目の出会いだった。(イシガ、鶴見、大岡さんももういない)
これら全集の編集作業は能登恵美子が献身的に取り組んだ。能登は2010年の『ハンセン病文学全集』の完結を見届けたかのように、東日本大震災・原発事故の4日前、2011年3月7日に逝った。あと数日で50歳になろうとしていた。
2000年代に『ハンセン病文学全集』と平行して取り組んできたのが、『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』のデータベース化だった。「これからの時代、データベースでなくては」と、データベース化の要請は強かったが、とてもわれわれにできる仕事とは思っていなかった。事実、NDLの「雑誌記事索引」にしても、NIIの CiNii にしても国の事業である。しかし、「どこもやらないなら、やってみよう」と、少しずつデータの入力を開始した。システムは某若手天才エンジニアが協力してくれた。『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』の入力を終え、次の段階として、雑誌の総目次の入力を始めた。戦後のデータはNDLから提供を受け、さらにCiNiiとの連携検索を実現し、2008年に明治期から現代までをカバーする唯一のデータベースとして「ざっさくプラス」の名前でサービスを開始した。現在は、他のデータベースが採録対象にしていない「戦前期」、「地方雑誌」、「植民地の雑誌(朝鮮語)」のほか、採録基準の見直しなどで空白期間の多いNDLのデータの補充(NDLのデータは、たとえば「婦人公論」の採録は1958年から1996年までの40年間が空白である)と、2014年からは提供を受けたものの目次データの粒度の粗いNDLのデジタルコレクションのメタデータの補完・作成を重点に追加を行っている。これによって、NDLのデジタルコレクション本体では本文画像はあるのに検索できないかなりの記事が「ざっさくプラス」を経由するとヒットする。このデータベースは現在2665万件のデータを搭載しているがこれは記事索引としては先行する諸データベースをしのいで日本最大となっている筈である。このデータベースもM社とK書店に販売を依頼したが、K書店からは断られた。まだアレが尾を引いているのかな。
長いこと一つの疑問があった。何故この試みをどこもやらなかったのかということだ。弊社の如き零細がやれたことだ、より大きな資本力のある会社がやれば弊社の出る幕はなかったのだ。しかし最近思い至った。まともな会社ならどのくらい先行投資をしてどのくらいの情報量になったら販売に転じ売上予測はどのくらいかなどと詳細に稟議書を書いて上長の決済を得ないと着手できない。検索して専門家が「あぁ、大体こんなもんか?」というのでは話にならない。「え、こんなものもあるの」という発見がなくては意味がない。これを僕は臨界点と呼ぶがデータベースはどれだけ入力したら臨界点に達するのかやってみないとわからない。やってみなくてはわからない事業にOKが出るわけがない。弊社はそんな手続き・検討なしで僕の一存で始めてしまった。つまり、まともでない零細の弊社だから出来た無謀な企画なのだ。もし、未だに臨界点に達していないならば先の見えない入力を続けるか先行投資を諦めて中断するしかない。思えば冷や汗ものだ。
水野広徳の著作を探すのに威力を発揮した戦前期の目録類であったが、現在「ざっさくプラス」で検索すると、水野は雑誌「新青年」に9編執筆している。これは「目録」では発見できなかったものだ。確認すると、収集した10万ページの「目録」には、ひとつとして「新青年」からとったものはない。つまり、現在では研究者の研究対象になっている「新青年」だが、当時の目録作成者から見たら採録対象外の通俗大衆雑誌だったのだ。「目録」は、作成者の手が入っている分、効率的ではあるが、その価値判断から外れたものは除かれてしまう。時代が変わって価値もまた変化した時、対応できない。しかしデータベース作成者は、価値判断をせずに片端からデータを搭載する。データベースは愚直に指示された条件で検索する。「目録」と「データベース」の違いである。
このデータベースは現在、海外60、国内120の大学図書館などに採用されている。
いくつかの単行本は制作したものの、30代を棒に振り、40歳で再出発後、『水野広徳著作集』を作り、この時集めた目録を『明治・大正・昭和前期 雑誌記事索引集成』として出版し、それを基に「ざっさくプラス」を作り、並行して『ハンセン病文学全集』を刊行した。
要約すればこのたった三行が僕の人生のまとめだよ。
スコセッシの最新作「アイリッシュマン」(2019年)で老殺し屋ロバート・デ・ニーロが言うではないか。「人は年を取らないと、時間の早さに気がつかない」。
諸兄諸姉!光陰矢の如し。少年老い易く学成り難いから、命短し恋せよ乙女だ。
終わり
(版元ドットコムの「版元日誌」に若干加筆訂正した。)
【関連リンク】ハンセン病資料館[不当解雇]問題について(2020年)